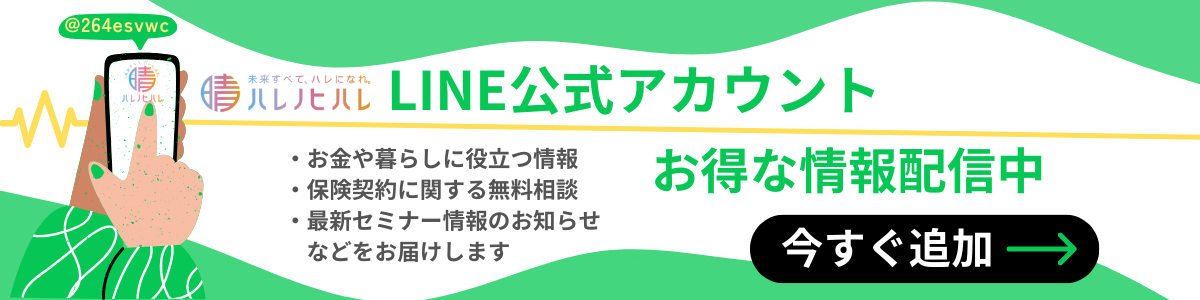iDeCoが向いている人・向いていない人は?メリット・デメリットを解説
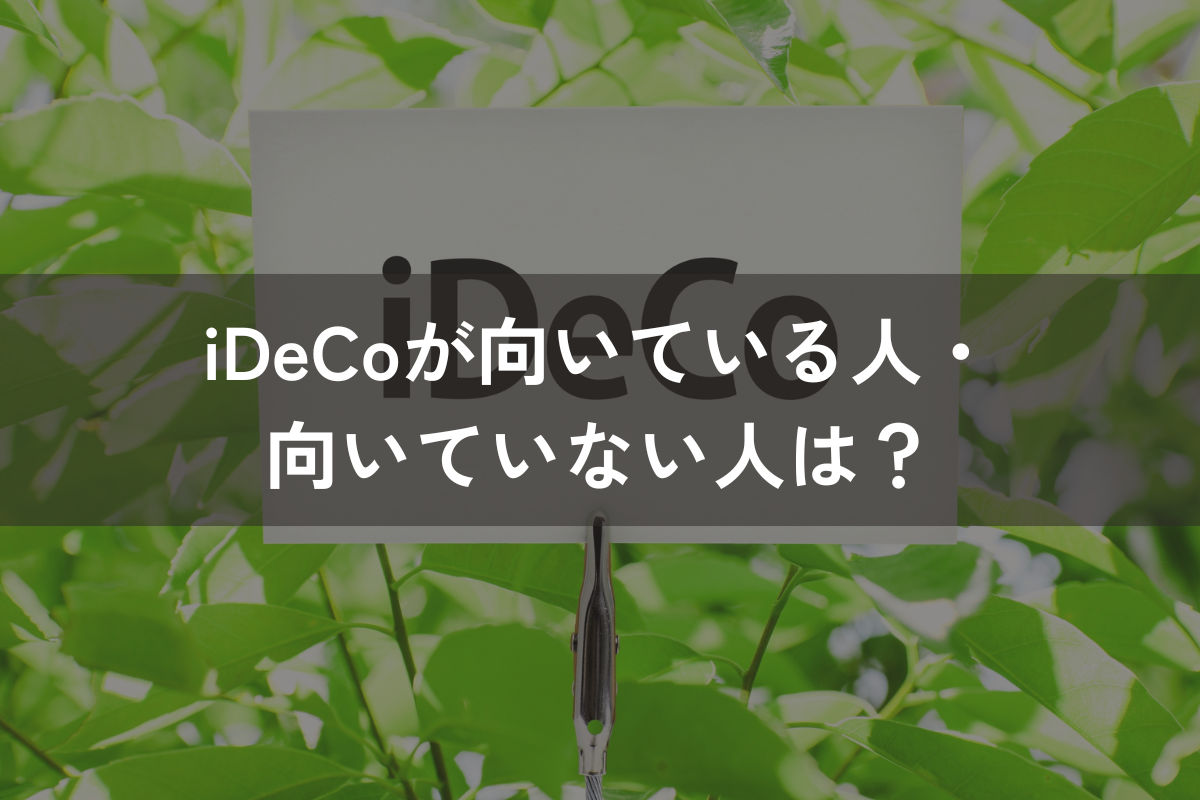
iDeCoに興味はあるものの、インターネットなどで「やめたほうがいい」という意見を目にする方もいらっしゃるでしょう。では、なぜiDeCoはやめたほうがいいといわれることがあるのでしょうか?
今回は、iDeCoがそもそもどういった制度なのか、「やめたほうがいい」といわれる理由、iDeCoの利用に向いている人・向いていない人などについて解説します。
ハレノヒハレは「未来すべて、ハレになれ。」を信念として、資産形成や保険見直しなどファイナンシャルプランナーがライフスタイルに合わせてアドバイスいたします。iDeCoについてお悩みの際は、ハレノヒハレまでお気軽にご相談ください(ご相談したいことがございましたら「お問い合わせ」フォームからご入力をお願いいたします)。
iDeCoはやめたほうがいいといわれる理由
iDeCoはやめたほうがいいといわれたことがある方もいらっしゃるでしょう。ここでは、iDeCoをやめたほうがいいといわれる主な理由を解説します。
- 加入資格を満たさないと利用できないから
- 積み立てたお金を60歳まで引き出せないから
- 運用方法次第で元本割れする可能性があるから
- 受け取り時に税金が発生する可能性があるから
- 所得次第では控除の効果を十分受けられない可能性があるから
- 掛金の上限が低いから
加入資格を満たさないと利用できないから
iDeCoは、公的年金制度の被保険者種別に、次のように分類されます。
| 公的年金の種別 | iDeCoの種別 | 該当者 |
|---|---|---|
| 1号被保険者 | 第1号加入者 | 20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、フリーランス、学生 |
| 2号被保険者 | 第2号加入者 | 会社員や公務員等の厚生年金の被保険者 |
| 3号被保険者 | 第3号加入者 | 2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 |
| 任意加入被保険者 | 第4号加入者 | 60歳以上65歳未満または20歳以上65歳未満の海外居住者で、国民年金の保険料の納付済期間が480月に達していない人が任意で加入 |
上記の分類別に、次の条件に該当する方はiDeCoを利用できません。
| 第1号加入者 | ・農業者年金の被保険者 ・国民年金保険料の納付を免除されている方 |
| 第2号加入者 | ・勤務先の企業型確定拠出年金に年単位で拠出している方 ・勤務先の企業型確定拠出年金で事業主掛け金に上乗せしてマッチング拠出している方 |
また、いずれの種別においても、次の方はiDeCoを利用できません。
- iDeCoの老齢給付金を受給したことがある方
- 老齢基礎年金、または特別支給の老齢厚生年金を繰り上げ受給している方
iDeCoの利用を考えている方は、まずは上記の条件を満たしているかを確認しなければなりません。
参照元:iDeCo(イデコ)の加入資格・掛金・受取方法等(iDeCo公式サイト)
積み立てたお金を60歳まで引き出せないから
iDeCoで積み立てたお金は、60歳まで引き出すことができません。毎月お金を積み立てていく必要がありますが、途中でお金が必要になったとしても、原則として積み立てたお金を使うことができないのです。
なお、iDeCoを60歳から受給するためにはiDeCoや企業型DCの通算加入者等期間の合計が10年以上ある必要があり、10年未満の方の受給開始年齢は次のように定められています。
| 加入期間 | 受給開始年齢 |
|---|---|
| 10年以上 | 60歳 |
| 8年以上10年未満 | 61歳 |
| 6年以上8年未満 | 62歳 |
| 4年以上6年未満 | 63歳 |
| 2年以上4年未満 | 64歳 |
| 1ヶ月以上2年未満 | 65歳 |
参照元:iDeCo(イデコ)の加入資格・掛金・受取方法等(iDeCo公式サイト)
運用方法次第で元本割れする可能性があるから
iDeCoで積み立てたお金は、投資信託などで運用することが可能です。運用する方法は自分で選ぶことができますが、選んだ運用方法次第では元本割れする可能性がある点に注意が必要です。
ただし、運用方法はiDeCoの口座を作成した金融機関次第で異なりますが、定期預金など元本割れしない方法で運用することもできます。
受け取り時に税金が発生する可能性があるから
iDeCoは積み立てた分のお金を所得税や住民税から控除できる制度ですが、60歳以降に受給する際には税金が発生する可能性があります。
iDeCoの受け取り方法には次の3つの方法があります。
- 一時金として一括で受け取る
- 年金として受け取る
- 一時金と年金を組み合わせて受け取る
上記のうち、一時金として受け取った分は退職所得として、年金として受け取った分は雑所得として課税の対象となる点に注意が必要です。
所得次第では控除の効果を十分受けられない可能性があるから
iDeCoは、積み立てた金額分、所得控除を受けられる制度です。このため、所得額次第では控除の効果を十分受けられない可能性がある点に注意しなければなりません。
たとえば、住宅ローン控除の適用を受け、住宅ローン控除の税額控除だけで全額控除を受けられる方は、iDeCoの所得控除の効果を十分得られない可能性があります。
掛金の上限が低いから
iDeCoには、第1号加入者、第2号加入者など種別ごとに掛金の上限が定められています。
| iDeCoの種別 | 拠出限度額 | |
| 第1号加入者 | 月額6.8万円 | |
| 第2号加入者 | 勤め先に企業年金がない会社員 | 月額2.3万円 |
| ・企業型DC・DBに加入している会社員 ・公務員 | 月額2.0万円 | |
| 第3号加入者 | 月額2.3万円 | |
参照元:iDeCo(イデコ)をはじめるまでの4つのポイント(iDeCo公式サイト)
なお、以前は公務員や企業年金制度に加入している会社員は上限が月額1.2万円でしたが、2024年12月より月額2.0万円まで引き上げられています。さらに、2027年1月より、1号加入者は月額7.5万円まで、2号加入者は月額6.2万円まで引き上げられる予定です。
iDeCoをやっている人はどのくらい?
iDeCoに加入している人の数は次のように右肩上がりで増加しています。日本国内で株価の上昇傾向が続いていることや、iDeCoの認知が広まっていることなどが背景として挙げられるでしょう。
| 年月 | 加入者数 |
|---|---|
| 2023年3月末 | 2,899,618人 |
| 2024年3月末 | 3,284,971人 |
| 2025年3月末 | 3,630,856人 |
| 2025年6月末 | 3,688,248人 |
| 2025年7月末 | 3,709,725人 |
参照元:「iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入者数等について(iDeCo公式サイト)
iDeCoに加入するメリット
iDeCoに加入する主なメリットとしては次のようなものが挙げられます。ここでは、iDeCoに加入する主なメリットを解説します。
- 掛け金を全額所得税・住民税から控除できる
- 運用で得られた利益は非課税で再投資できる
- 60歳に受け取る際は所得控除を受けられる
- 指定口座からの自動引落しで自然と積立できる
- 引き出しできないからいやでもお金が積み立てられる
- インフレに強い
掛金を全額所得税・住民税から控除できる
iDeCoは、掛金を全額所得税・住民税から控除できます。単に投資信託に投資するのと比較すると、投資金額の全額を所得控除できるiDeCoを利用するメリットは大きいといえるでしょう。
運用で得られた利益は非課税で再投資できる
通常、株式や投資信託で資産を運用して得られた利益に対しては税金が課されます。しかし、iDeCoの場合、運用で得られた利益は非課税です。
また、iDeCoは原則として途中で引き出すことができないこともあり、運用で得られた利益は全額再投資されます。このため、長く運用するほど複利による大きな効果を得ることが可能です。
複利効果とは、運用で得られた利息や利益を元本に組み入れて再投資することで、その利息が新たな利息を生み出し、資産が「雪だるま式」に増えていく仕組みのことです。
たとえば、年間30万円を1年間運用して10%の利益が得られた場合、次の年は33万円(=30万円×110%)になり、またその次の年は36.3万円(=33万円×110%)になるといった効果のことです。もちろん、必ずしも資産の運用結果がプラスにあるとは限りませんが、長期的に運用していくことで高い効果を得やすくなっています。
60歳に受け取る際は所得控除を受けられる
iDeCoを60歳以降に受給する際は、年金方式の場合は雑所得、一時金方式の場合は退職所得として税金が課される可能性があります。一方、年金方式の場合は公的年金等控除を、一時金方式の場合は退職所得控除を受けられるというメリットもあるのです。
特に退職所得控除は、勤務年数に応じて1,000万円以上の控除を受けられる可能性があります。他の保険商品等の利用状況と合わせて、控除を賢く活用することが大切です。
指定口座からの自動引落しで自然と積立できる
iDeCoは、毎月指定口座から自動引落しで積立できます。そのため、手元にお金があってもつい使ってしまうという方であっても、半強制的にお金を貯めていくことができる点はメリットだといえるでしょう。
引き出しできないからいやでもお金が積み立てられる
原則として、iDeCoは途中で解約できません。そのため、まとまったお金が必要になるようなことがあっても、引き出すことができません。この点はデメリットだといえますが、一方で強制的にお金を貯めることができるという点ではメリットだということもできるでしょう。
老後資金に不安を感じている方は多いことと思います。iDeCoを活用することで、半強制的に老後資金を貯めていくことが可能です。
インフレに強い
iDeCoを活用することは、選択する金融商品によってインフレ対策につながります。インフレとは、「インフレーション」の略称で、モノやサービスの価格(物価)が持続的に上昇し、その結果としてお金の価値が目減りする現象のことを指します。
投資信託などの金融商品に積み立てておけば、インフレが進みお金の価値が下がると、金融商品の価値が相対的に高くなりやすいという特徴があります。
なお、iDeCo口座を開設する金融機関によっては、不動産や金に連動する投資信託などの商品もあります。これら、実物資産に投資するタイプの投資信託は一般的にインフレに強いです。
よりインフレに強い金融商品で運用したいという方は、そういった商品へ投資することも可能です。
iDeCoに向いていない人の特徴
iDeCoにはさまざまなメリットがありますが、一方で次のような方は、iDeCoは利用しないほうが良いといえるでしょう。
- 収入が安定しない人
- 収入が少ない人
- 貯蓄が少ない人
- 大きなお金を使う予定がある人
収入が安定しない人
iDeCoは、事前に設定した金額を毎月積み立てる必要があります。そのため、収入が安定しないと負担になってしまう可能性があります。個人事業主の方や、営業職で歩合制の方など、収入に波がある方はiDeCoの利用には慎重になる必要があるでしょう。
なお、iDeCoで設定した金額に対して、金融機関の口座に残高がない場合、積立はされず、特にペナルティなどもありません。
収入が少ない人
毎月の収入が少ない人も同様に、iDeCoに向いていないといえるでしょう。
iDeCoは老後のために積み立てる制度ですが、老後を考えるあまり、今の生活が疎かになってしまっては本末転倒です。収入に対して、毎月必要な生活費の額などを確保したうえで、無理なく積立できる額を積み立てていくことが大切です。
貯蓄が少ない人
iDeCoでは、積み立てたお金を途中で引き出すことができません。
生活していく中で、家族の大きな病気などまとまったお金が必要になるタイミングがあるでしょう。そうしたときに、貯蓄が少ないと対応できなくなってしまうことが考えられます。
iDeCoは、老後のための資金を積み立てる制度です。手元に十分な貯蓄がない方は、まずはある程度の貯蓄を作ることから始めると良いでしょう。
大きなお金を使う予定がある人
子どもの進学や自動車の買い替え、マイホームの購入、海外旅行など大きなお金を使う予定がある人も注意が必要です。ある程度の貯蓄がある人でも、これらのライフイベントにより手元のお金が少なくなってしまうことが考えられます。
手元のお金がなくなってしまっても、iDeCoに積み立てたお金は原則として途中で引き出すことができません。大きなお金を使う予定が決まっているという方は、どの程度のお金が必要になるかを試算し、お金を使った後の生活をシミュレーションしたうえで、iDeCoを利用するかどうかや拠出額を決めることが大切だといえます。
iDeCoに向いている人の特徴
一方、次のような方はiDeCoに向いているといえるでしょう。
- 安定した収入がある人
- お金があると使ってしまう人
- 資産運用したい人
- 退職金がない、もしくは少ない人
安定した収入がある人
毎月安定した収入があり、毎月余分になるお金があるといった人は、iDeCoを利用することで節税効果を活用しつつ、老後資金を貯めていくことができます。
ただし、先ほども解説したように、iDeCoで積み立てたお金は原則として途中で引き出すことができません。そのため、ある程度は貯蓄したうえで、さらに余裕のある資金をiDeCoに積み立てるといった利用方法がお勧めです。
お金があると使ってしまう人
手元にお金があると使ってしまうという方は、iDeCoの利用がお勧めです。
iDeCoは事前に指定した金額を指定した口座から天引きする形で積み立てていくことができます。また、積み立てたお金は自分の意志で引き出すことができません。
そのため、毎月ある程度の余裕があるはずなのにも関わらず、なぜか手元にお金が残らないといった方は、iDeCoを活用することで半強制的にお金を貯めていくことができるでしょう。
資産運用したい人
iDeCoは、自分で積み立てたお金を、投資信託や定期預金などの運用商品に振り分けて資産を増やしていける制度です。積み立てた金額はそのまま所得控除の対象となり、運用で得られた利益も課税されず自動的に再投資されます。これにより、通常の証券口座で投資を行う場合に比べて、税制面で有利に効率良く資産形成を進めることができます。
なお、iDeCoと合わせて検討されることの多いものにNISAがあります。NISAは、NISA口座内で投資した商品の運用益が非課税になるという制度です。iDeCoと似た制度ではありますが、iDeCoは積み立てた額の全額を所得控除できるため、さらに大きな節税効果を得られる制度だといえるでしょう。
一方で、NISAはiDeCoのように60歳にならないと引き出せないといった制限がありません。それぞれの特徴を理解して、より自分の状況に適した資産運用方法を選ぶことが大切です。
退職金がない、もしくは少ない人
iDeCoでは、60歳以降に積み立てたお金を受給できます。そのため、勤めている企業で退職金制度がない人、もしくは少ない人は、iDeCoを使って自分で積み立てることで老後資金の問題を解消しやすくなるでしょう。
iDeCoに関するよくある質問
最後に、iDeCoに関するよくある質問とその回答を4つ紹介します。
iDeCoがデメリットしかないといわれる理由は?
特に大きなデメリットとなりやすいのが、途中で資金を引き出すことができないという点です。
お金の価値は、若い時期ほど高いと考えられることがあります。若いうちにお金を活用して多様な経験を積むことで、人生の充実度を高めやすいからです。一方で、若い世代は収入水準が比較的低く、iDeCoへの拠出が家計にとって負担になりやすいという側面もあります。
一方で、iDeCoを利用することで、積立額分を全額所得控除できるといったメリットがあります。また、若いうちに積み立てることで、より大きな複利効果を得やすいこともポイントです。
iDeCoにはデメリットもありますが、さまざまなメリットもあります。iDeCoを利用する際には、収入から生活費を差し引いた残りの金から、さらにある程度の貯蓄をして、さらに残ったお金をiDeCoで積み立てるといった対策をすることで、iDeCoのメリットを活用しやすくなるといえます。
iDeCoで積み立てる金額が毎月1万円では意味がない?
iDeCoで毎月1万円を積み立てても、年間で12万円、10年間で120万円にしかなりません。30歳から60歳まで30年間積み立てても、360万円にしかならないのです。
とはいえ、掛金1万円で意味がないということはありません。まず、iDeCoの毎月の掛金は毎月所得控除されます。特に、所得税や住民税を安く抑えたいという方にとっては大きなメリットとなるでしょう。
また、iDeCoでは運用益が全額非課税で再投資されます。そのため、長期間投資することで大きな複利効果を得ることが可能です。
たとえば、掛金を年間12万円として、毎年5%の運用益が得られた場合の30年間の運用結果を表にすると、下のようになります。
| 年数 | 再投資額 | 運用益5%を加算した額 |
|---|---|---|
| 1年目 | ¥120,000 | ¥126,000 |
| 2年目 | ¥246,000 | ¥258,300 |
| 3年目 | ¥378,300 | ¥397,215 |
| 4年目 | ¥517,215 | ¥543,076 |
| 5年目 | ¥663,076 | ¥696,230 |
| 10年目 | ¥1,509,347 | ¥1,584,814 |
| 15年目 | ¥2,589,428 | ¥2,718,899 |
| 20年目 | ¥3,967,914 | ¥4,166,310 |
| 25年目 | ¥5,727,252 | ¥6,013,614 |
| 30年目 | ¥7,972,662 | ¥8,371,295 |
積み立てた額は360万円ですが、最終的な運用結果は約837万円と2倍以上の結果となっていることがわかります。
もし毎年5%以上の結果が得られれば、さらに大きな運用益を得ることが可能です。とはいえ、必ずプラスになるわけではないという点には注意しなければなりません。
iDeCoで元本割れする確率は?
iDeCoで元本割れする確率を算出することはできません。そもそも、iDeCoだから元本割れするということはありません。
iDeCoでは、加入した金融機関によって、さまざまな運用方法を選ぶことが可能です。定期預金など、元本割れしない方法で運用することで、元本割れを回避することができるでしょう。
iDeCoの利用にお悩みの際は「ハレノヒハレ」にご相談ください
iDeCoは掛金全額分の所得控除を受けられる制度ですが、そもそも所得が高くないと満額の控除を受けられないなど注意しなければならない点があります。一定の安定した所得があるなど、iDeCoの利用には向いている人と向いていない人がいるため、今回解説した内容をご参考ください。
とはいえ、ご自身だけで検討するのは容易ではありません。iDeCoを始める際は、プロに相談することから始めるのがお勧めです。
ハレノヒハレは「未来すべて、ハレになれ。」をコンセプトに、資産形成や家計の見直しなどのサポートをしています。iDeCoを含め、老後の資金に困ることなく賢く運用していきたいとお考えの際などには、ハレノヒハレまでお気軽にご相談ください(ご相談したいことがございましたら「お問い合わせ」フォームからご入力をお願いいたします)。