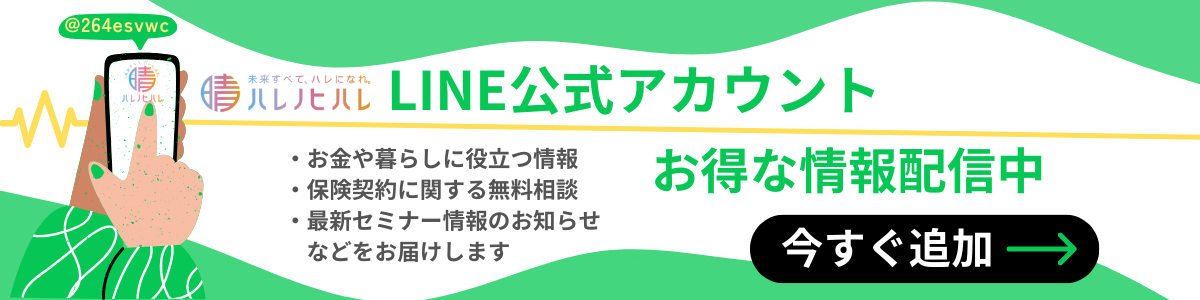無理なくコツコツ貯める方法は?お金を貯めるコツやポイントも解説

「貯蓄をしようにも、まとまったお金が捻出できない」とお悩みの方も少なくないのではないでしょうか?しかし、たとえ少額からであっても貯蓄はでき、定期的にコツコツ貯めることには多くのメリットが存在します。
では、お金をコツコツ貯めることにはどのようなメリットがあるのでしょうか?また、コツコツと資産形成をする方法には、どのようなものが挙げられるでしょうか?今回は、コツコツとお金を貯めるメリットや貯めるお金を捻出する方法、コツコツと資産形成をするのにお勧めの方法などについてくわしく解説します。
ハレノヒハレは「未来すべて、ハレになれ。」をコンセプトに、資産形成や家計見直しなどのサポートをしています。将来へ向けてコツコツと資産形成をしたいとお考えの際などには、ハレノヒハレまでお気軽にご相談ください(ご相談したいことがございましたら「お問い合わせ」フォームからご入力をお願いいたします)。
お金をコツコツ貯めるメリット
お金をコツコツ貯めることには、さまざまなメリットがあります。はじめに、お金をコツコツ貯める主なメリットを4つ解説します。
- 貯蓄を習慣化しやすい
- 積み重なると大きな額になりやすい
- 貯蓄を差し引いた分での生活に慣れることで、万が一の収入減少時に対応しやすい
- 投資信託などの場合「ドルコスト平均法」のメリットを享受できる
貯蓄を習慣化しやすい
1つ目は、貯蓄を習慣化しやすくなることです。資産形成は一朝一夕に実現できるものではなく、継続こそが重要であるといえます。
たとえ少額からであってもコツコツとお金を積立てることで貯蓄の習慣化が可能となり、資産形成を成功させやすくなります。
積み重なると大きな額になりやすい
2つ目は、積み重なると大きな資産になりやすいことです。仮に月々1万円の貯蓄であっても、これを毎月継続すれば、利息を加味しなくとも1年間で12万円、10年続ければ120万円もの資産が形成できます。
もちろん、毎月の貯蓄額が多ければ、さらに大きな資産形成が可能です。コツコツと資産を積み立てることで、たとえば子どもの大学入学費用など、将来の大きな支出に備えやすくなるでしょう。
貯蓄を差し引いた分での生活に慣れることで、万が一の収入減少時に対応しやすい
3つ目は、貯蓄を差し引いた分での生活に慣れることで、万が一の収入減少時に対応しやすくなることです。
一般的に、一度上がった生活水準を下げるのは容易ではありません。とはいえ、特に自営業などの場合には現在の収入がいつまでも続く保証は乏しく、将来的に収入が下がる可能性も否定できません。
そこで、たとえば1ヶ月あたりの手取り収入が50万円であっても、このうち10万円や15万円を貯蓄や収入減少時の備えに回し、日頃から1ヶ月あたり40万円や35万円で生活することに慣れておくことで、万が一収入が減少した場合であってもスムーズに順応しやすくなります。
投資信託などの場合「ドルコスト平均法」のメリットを享受できる
4つ目は、投資信託などで資金を積み立てる場合、「ドルコスト平均法」のメリットを享受しやすくなることです。ドルコスト平均法とは、価格が変動する投資信託などの金融商品を、その時の価格に関わらず、定期的に定額を買い続ける投資手法です。
たとえば、ある投資信託について、「毎月末日に5,000円分ずつ購入する」ことなどがこれに該当します。購入時点においてその投資信託の価格が高ければ5,000円で購入できる口数が少なくなる一方で、投資信託の価格が下がっていれば5,000円で購入できる口数が多くなります。
投資の鉄則としてよく言われるものに、「長期・分散・積立投資」があります。これは、長期にわたって複数の金融商品にコツコツ積み立てて投資することで投資のリスクを分散でき、長期的な資産形成に役立つとされる考え方です。ドルコスト平均法はこの鉄則に合致しており、資産形成の基本形と言えるでしょう。
たとえば、1年に1回など低頻度でまとまった額を投資に回すのではなく、毎月コツコツと積み立てることでこの「ドルコスト平均法」を実現でき、「長期・分散・積立投資」のメリットを享受しやすくなります。
貯めるお金を捻出する方法
コツコツとお金を貯めようにも、貯めるための資金が用意できない場合もあるでしょう。ここでは、貯めるお金を捻出する主な方法を解説します。
- 収入を増やす
- 固定費を削減する
- 変動費を削減する
収入を増やす
コツコツ貯める原資を捻出する方法としては、収入を増やすことが挙げられます。収入を増やす主な方法には、次のものなどが挙げられます。
- 勤務先で昇給を目指す
- 勤務先からの資格手当などの受給を目指す
- 副業でアルバイト収入を得る
- 副業でフリーランスとして収入を得る
- 着られなくなった子ども服・靴などを定期的にフリマアプリで売却する
ただし、会社によっては就業規則などで副業を禁止したり事前承認制としたりしている場合もあるため、副業による収入アップを目指す際は勤務先の規定を事前に確認しておくべきでしょう。副業を制限する規定があるにもかかわらず勤務先に無断で副業をすれば、懲戒処分の対象となる可能性があり、収入が減る事態を招くおそれがあるためです。
固定費を削減する
コツコツ貯める原資を捻出する方法としては、固定費の削減が検討できます。固定費とは、家計の支出のうち、毎月おおむね定額となる項目です。具体的には、次の方法などが検討できます。
- 自動車を売却してカーリースやタクシーを使い、自動車維持費を削減する
- 携帯電話を格安スマホに変えて、通信費を削減する
- 保険を見直して保障の重複を避け、保険料を削減する
- 電気料金プランを見直して、光熱費を削減する
- 利用頻度の低いサブスクを解約する
固定費を一度見直すと、その効果は一定期間継続します。そのため、家計の支出を抑えるには、まず固定費の削減から検討するとよいでしょう。
変動費を削減する
変動費とは、家計の支出のうち、その月ごとに支出額が変動する項目です。変動費の削減も貯蓄原資の捻出方法として有効ではあるものの、「外食を1回我慢する」などその場限りの削減に終わらない工夫が必要でしょう。
変動費の削減方法としては、次のものなどが検討できます。
- 1ヶ月あたりの外食回数(または、外食費)に上限を設け、食費を削減する
- ワンシーズンあたりの被服の買い物回数(または、金額)に上限を設け、被服費を削減する
- ワンシーズンあたりの旅行回数(または、金額)に上限を設け、娯楽費を削減する
その場限りの「我慢」に頼るのではなく、このように一定のルールを設けることで変動費のコントロールが可能となり、家計の改善につながります。
ハレノヒハレは「未来すべて、ハレになれ。」をコンセプトに、家計改善や資産形成などのサポートをしています。資産形成方法や貯蓄原資の捻出についてプロに相談したいとお考えの際などには、ハレノヒハレまでお気軽にご相談ください(ご相談したいことがございましたら「お問い合わせ」フォームからご入力をお願いいたします)。
お金をコツコツ貯めるポイント
お金をコツコツ貯めるには、どのようなポイントを押さえればよいのでしょうか?ここでは、主なポイントを4つ解説します。
- 無理のない貯蓄額を設定する
- 「残った分を貯蓄する」のではなく先に貯蓄に回す
- 家計簿をつける
- お金を貯める目的を明確にする
無理のない貯蓄額を設定する
コツコツお金を貯めるポイントの1つ目は、無理のない貯蓄額を設定することです。
貯蓄額に無理があれば、貯蓄を継続するのは困難です。また、生活費が不足してせっかく貯めたお金を目的以外の用途で切り崩すことが常態化すれば、いつまで経ってもお金が貯まらない事態となりかねません。
無理のない貯蓄額を設定することで、貯蓄を継続しやすくなります。
「残った分を貯蓄する」のではなく先に貯蓄に回す
コツコツお金を貯めるポイントの2つ目は、「残った分を貯蓄する」のではなく、先に貯蓄に回すことです。
貯蓄を計画する場合、「まずは生活費などでお金を使い、残った分を貯蓄しよう」と考える場合もあるでしょう。しかし、この方法で貯蓄を継続させるのは容易ではありません。
残った額を貯蓄に回すのではなく、収入を得たら貯蓄すべき額を先に差し引いて貯蓄用の口座に移すことで、計画的な貯蓄を成功させやすくなります。
家計簿をつける
コツコツお金を貯めるポイントの3つ目は、家計簿をつけることです。
家計簿をつけることで家計の状態が「見える化」でき、出費の嵩みやすい項目を把握しやすくなります。不要な出費を減らして家計をスリム化することで貯蓄の原資が捻出でき、貯蓄を継続しやすくなるでしょう。
お金を貯める目的を明確にする
コツコツお金を貯めるポイントの4つ目は、お金を貯める目的を明確にすることです。
貯蓄の目的が明確でない場合には貯蓄のモチベーションが上がりづらく、貯蓄が続かないかもしれません。たとえば、「子どもの大学入学資金に備えたい」や「老後資金を積立てておきたい」など貯蓄の目的を定めることで貯めるべき金額も明確になり、計画的に貯蓄を続けやすくなります。
お金をコツコツ貯めるのにお勧めの方法は?
お金をコツコツ貯めるには、どのような方法があるのでしょうか?ここでは、お金をコツコツ貯めるお勧めの方法を5つ紹介します。
- 定期預金
- 個人年金保険
- 学資保険
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
- NISA(少額投資非課税制度)のつみたて投資枠
定期預金
1つ目は、定期預金です。普通預金からの定期的な積立設定ができる金融機関も多く、安定的な資産形成に役立ちます。
これらは原則として元本割れのリスクがないため、投資のリスクを避けたい方にも適した金融商品であるといえます。万が一金融機関が破綻した場合には、預金保険制度により、一般の預金は「金融機関ごとに元本1,000万円とその利息まで」保護されます。1行あたりの預け入れが1,000万円を超える場合は、複数行に分散するなどの方法でリスクを抑えられます。定期預金や定期積金はリスクが低い商品である反面、大きなリターンを得ることも困難です。また、一般的にインフレリスク(インフレが起きて物価が上昇することで、相対的に資産価値が低下するリスク)への対応が難しいことにも注意しなければなりません。
個人年金保険
2つ目は、個人年金保険です。
個人年金保険とは、民間の保険会社との契約により、自分で準備する年金です。公的年金だけでは将来の生活費に不安を感じる場合などに、公的年金を補完する目的で加入することが多いでしょう。たとえば、30代や40代など比較的若いうちからコツコツと保険料を支払ってこれを原資として運用し、60歳や65歳、70歳など所定の年齢から年金として受け取ることが一般的です。
受け取り期間は10年や15年など一定期間とする場合もある一方で、被保険者が生存している限り受け取れる終身とする場合もあります。一口に「個人年金保険」といっても、その具体的な内容は商品ごとに異なります。そのため、契約内容を十分に理解したうえでご自分に合った商品を選びましょう。
学資保険
3つ目は、学資保険です。
学資保険とは、子どもの教育資金の準備に特化した、貯蓄型の生命保険です。具体的な内容は商品ごとに異なりますが、一般的には子どもが幼いうちからコツコツと保険料を支払い、子どもの高校入学時や大学入学時にまとまった保険金を受け取るものが多いでしょう。
将来の教育資金は預貯金口座にコツコツ貯めていくこともできるものの、預貯金口座では別の用途に流用しやすいことが難点です。その点、学資保険は解約すれば元本割れするおそれもあるため、中途解約のハードルは預貯金よりも高いでしょう。そのため、別の用途に流用しづらく、計画的に教育資金を用意しやすいといえます。
また、学資保険は「保険」であるため、契約者である世帯主の死亡にも備えられます。保険料の払い込み期間中に万が一契約者が亡くなるなどした場合には以後の保険料の払い込みが免除される一方で、保険金は契約通りに支払われます。そのため、万が一世帯主が亡くなっても、必要な教育資金を準備しやすくなるでしょう。
ただし、学資保険だけではインフレリスクへの対応は難しいことが一般的です。たとえば、契約時点の物価を踏まえて子どもの大学入学時期に300万円を受け取れる学資保険に加入する場合、インフレが起きて実際に大学に入学する際には必要な学費が2倍になっていたとしても受け取れる保険金は一般的に契約で定めた300万円のままであり、2倍の600万円にはならないということです。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
4つ目は、iDeCo(個人型確定拠出年金)です。
iDeCoとは、自分が拠出した掛金を自分で運用し、資産を形成する年金制度です。掛金は原則として65歳になるまで拠出でき、原則として60歳以降に老齢給付金として受け取ります。
iDeCoの掛金の上限額は加入者の区分によってことなっており、自営業者などの第1号被保険者であれば1ヶ月あたり6.8万円、会社員などの第2号被保険者は勤務先の会社が設けている年金制度などに応じて1ヶ月あたり2.3万円/2万円/1.2万円、会社員の配偶者などの第3号被保険者は1ヶ月あたり2.3万円です。
※いずれも制度や勤務先の規程により変わる場合があります。
必ずしも上限までを拠出する必要はなく、月々5,000円からの拠出が可能であるため、コツコツ資産形成をしようとする際はiDeCoへの加入を検討するとよいでしょう。拠出額は全額が所得控除の対象となるなど、iDeCoには税制面のメリットもあります。
参照元:iDeCoの特徴|iDeCoってなに?(iDeCo公式サイト)
NISA(少額投資非課税制度)のつみたて投資枠
5つ目は、NISA(少額投資非課税制度)のつみたて投資枠です。
NISAとは、株式や投資信託などの金融商品に投資することで得た売却益や配当・分配金にかかる20.315%の税金が、一定の条件のもとで非課税になる制度です。運用益が税金によって目減りしないため、より効率的な資産形成がしやすくなります。
NISAには、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2つの枠があります。このうち成長投資枠は上場株式や投資信託等を対象とする投資枠であり、単発での購入も対象となります。
一方で、つみたて投資枠とは長期の積立・分散投資に適するとして金融庁の基準を満たした一定の投資信託を定期的に購入する投資枠であり、毎月コツコツと投資信託を購入し資産形成をすることなどに適しています。先ほど解説した「ドルコスト平均法」による資産形成では、このつみたて投資枠の活用を検討するとよいでしょう。
成長投資枠とつみたて投資枠は併用できるため、非課税枠を上手に活用しつつまずは少額の投資からはじめ、徐々に自分に合った資産形成方法を見つけていくことをお勧めします。
お金を貯めることに関してよくある質問
最後に、お金を貯めることに関するよくある質問に3つ回答します。
少ない収入でお金を貯める方法は?
少ない収入でお金を貯めるには、収入が入った時点で貯蓄したい額を先に差し引き、貯蓄に回す方法が検討できます。ただし、生活費が不足した結果貯蓄を取り崩す事態が常態化すれば本末転倒であるため、無理のない貯蓄額を設定するのもポイントです。
少額からの貯金でもよい?
貯蓄は、少額から始めても構いません。特に、これまで貯蓄の習慣がなかった場合には、少額からであってもまずは貯蓄をする習慣を付けることが重要です。
長期・分散・積立投資って実は難しいといわれるのはなぜ?
長期・分散・積立投資が難しいといわれる理由は、結果がすぐには出づらく、モチベーションが続きにくいことにあります。また、「本当にこれでよいのか」と不安になり、途中で投資をやめてしまう場合があることも理由の1つでしょう。
しかし、資産形成はすぐに結果が出るものではなく、コツコツと継続してこそ効果が得られるものです。資産形成をご希望の際は、プロからアドバイスを受けることをお勧めします。
プロにアドバイスを受けることでご自分に合った資産形成方法が把握しやすくなるほか、自信をもって資産形成を継続しやすくなるためです。
まとめ
お金をコツコツ貯めるメリットやお金をコツコツ貯めるポイント、コツコツ貯めるのにお勧めの方法などを解説しました。
お金をコツコツ貯めるメリットには、貯蓄を習慣化しやすいことや積み重なると大きな額になりやすいこと、「ドルコスト平均法」のメリットを享受しやすいことなどが挙げられます。資産形成にはある程度の時間が必要であり、時間をかけてコツコツとお金を積み立てることで投資の基本である「長期・分散・積立投資」を実現しやすくなるでしょう。
お金をコツコツ貯める方法としては、定期預金のほかに、個人年金保険や学資保険、NISA・iDeCoの活用などが挙げられます。ご自分に合った資産形成方法を知りたい場合には、1人で悩むのではなく、まずはプロに相談するのがお勧めです。
ハレノヒハレは「未来すべて、ハレになれ。」をコンセプトに、資産形成や家計改善などのサポートをしています。ご自分に適した資産形成方法についてプロに相談したいとお考えの際などには、ハレノヒハレまでお気軽にご相談ください(ご相談したいことがございましたら「お問い合わせ」フォームからご入力をお願いいたします)。