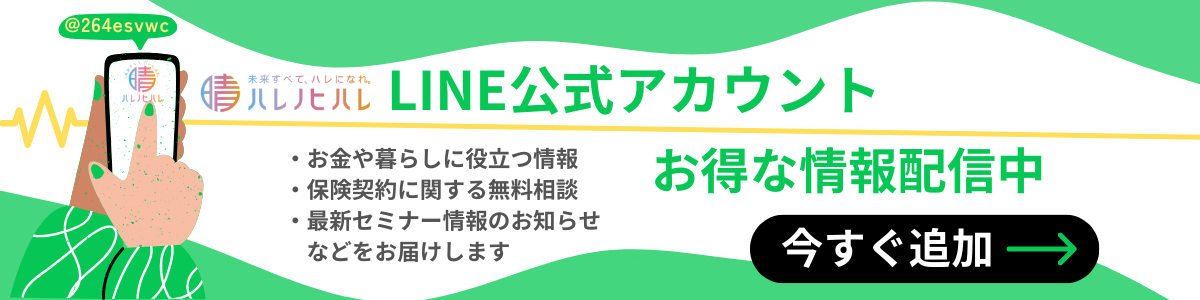20代で貯金300万円は多い?少ない?平均的な貯蓄額や貯金のコツをわかりやすく解説

20代はライフステージの変化も多く、本格的に貯金を始めようと考える人も少なくないでしょう。そこで気になるのが、20代での貯金の平均額です。
20代で貯金額が300万円である場合、これは平均値よりも少ないのでしょうか?また、20代で貯金を成功させるには、どのようなポイントを押さえれば良いのでしょうか?今回は、20代の貯金に関するデータを紹介するとともに、20代で備えておきたい主なライフイベントや20代が貯金を成功させるポイントなどについてくわしく解説します。
なお、ハレノヒハレは「未来すべて、ハレになれ。」を信念として、家計見直しや資産形成などファイナンシャルプランナーがライフスタイルに合わせてアドバイスいたします。資産形成などについてお悩みの際は、ハレノヒハレまでお気軽にご相談ください(ご相談したいことがございましたら「お問い合わせ」フォームからご入力をお願いいたします)。
20代の貯金額のデータ
20代で貯金が300万円ある場合、これは多いのでしょうか?それとも少ないのでしょうか?まずは、20代の貯金額のデータを紹介します。
【単身世帯】20代の平均貯蓄額
金融広報委員会が公表している「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和5年)」によると、単身世帯の20代の金融資産保有額を割合の高かった順に並べると、上位は次のとおりでした。
| 金融資産非保有 | 43.9% |
| 100万円未満 | 23.0% |
| 100~200万円未満 | 10.9% |
| 200~300万円未満 | 5.3% |
| 300~400万円未満 | 4.9% |
また、金融資産保有額の平均値は121万円、中央値は9万円です。金融資産をまったく有していない世帯が多いほか、金融資産非保有世帯と100万円未満の合計が全体の約3分の2を占めている状態です。
一口に「20代」といっても、21歳と29歳とではライフステージや社会人経験などが大きく異なります。これは単身世帯のデータであることから若年層の比率が相対的に高く、平均が低めに出やすいと予想され、貯蓄額が全体的に低くなっているものと考えられます。
また、20代の単身世帯であれば、貯金の必要性をさほど感じていない場合も少なくないでしょう。
【2人以上世帯】20代の平均貯蓄額
金融広報委員会が公表している「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和5年)」によると、世帯主が20代である2人以上の世帯の金融資産の保有額は次のとおりでした。
| 金融資産非保有 | 36.8% |
| 100万円未満 | 21.6% |
| 100~200万円未満 | 9.9% |
| 200~300万円未満 | 8.2% |
| 300~400万円未満 | 4.7% |
| 400~500万円未満 | 4.7% |
また、金融資産保有額の平均値は249万円、中央値は30万円です。金融資産非保有世帯の割合も多い一方で、単身世帯と比較すると貯蓄額の平均値や中央値などがやや高くなっていることがわかります。
20代で貯金300万円は多い?少ない?
先ほど紹介したデータに照らし合わせると、20代での貯金300万円は決して少ない額ではなく、むしろ平均よりも高い貯蓄額であるといえます。
計画的に資産形成を行うことで、今後訪れるライフイベントに対応しやすくなることから、今後も計画的な貯蓄を継続すると良いでしょう。
20代の貯金額の平均値を調べる際に理解しておくべきこと
ここまでで20代での貯金額(金融資産)のデータを紹介したものの、これを自分の貯金額と比較して一喜一憂することはお勧めできません。なぜなら、必要となる貯金額は、具体的な状況や理想のライフスタイルなどによって大きく異なるためです。
たとえば、すでに持ち家を有している人とこれから持ち家を買おうとしている人とでは、必要な貯金額は異なります。また、将来的に子どもを持つ予定のない人とすでに2人の子どもがいる人とでも、望ましい貯金額は異なるでしょう。
さらに、親が所有する土地に地元工務店で建物を建てて暮らそうとしている人と都心のタワマンで暮らしたいと考えている人、子どもに海外留学をさせたいと考えている人とそのような予定のない人、毎年1回は海外旅行に行きたいと考えている人と旅行にさほど興味のない人など、ライフスタイルや理想の生活の形などによって、必要な貯金額は大きく左右されます。
そのため、「平均値」だけを気に掛けるのではなく、まずは自分や家族が望む生活を念頭に置いたうえで、これを実現するために必要な貯金額を「逆算」して検討すべきでしょう。
そのためには、まずはファイナンシャルプランナーに相談したうえで、ライフプランを作成することをお勧めします。ライフプランを作成することで必要となる金額が明確となり、そこから「逆算」をすることでご自分にとって望ましい貯金額が把握できます。
ご自分にとって必要な貯金額を知りたい際は、ハレノヒハレまでお気軽にご相談ください(ご相談したいことがございましたら「お問い合わせ」フォームからご入力をお願いいたします)。
20代で備えておきたい主なライフイベント
先ほど解説したように、20代や次の30代ではさまざまなライフイベントが起きる可能性があります。ここでは、20代で備えたい主なライフイベントの概要について解説します。主なライフイベントやそれぞれに要する費用の目安を知っておくことで、自分にとって必要な貯金額を把握しやすくなるためです。
- 自動車の購入
- 結婚
- 出産
- 住宅の購入
自動車の購入
20代では、マイカーを購入する人も多いでしょう。公共交通機関の利便性が高い都心など一部の地域以外では、自動車がなければ日常生活が困難な地域も多く、そのような地域では自動車の購入は必須といえます。
一般社団法人日本自動車工業会が2024年3月に公表した「2023年度乗用車市場動向調査」によると、2023年の新車の平均購入価格は264万円でした。この新車平均購入価格は2021年は255万円、2019年は245万円であり、徐々に価格が上昇しています。
購入したい自動車がある場合には、事前に価格を調べたうえで、計画的に貯金を進めると良いでしょう。
結婚
20代やその後訪れる30代では、結婚をする可能性があります。結婚をするすべての人が挙式をするわけではないとはいえ、挙式をしようとすればそれなりのお金が必要です。
参考までに、「ゼクシィ結婚トレンド調査2024」の首都圏版によると、2024年調査における首都圏の「挙式、披露宴・ウエディングパーティー総額」の平均額は374.8万円でした。
また、新婚旅行に出かけたり婚約指輪・結婚指輪を用意したりすれば、さらに費用がかかります。加えて、新居への引っ越しや新居で使用する家具の購入などにかかる費用も準備しなければなりません。
そのため、挙式・披露宴を行うか否かも検討したうえで、計画的に貯金を進める必要があります。
出産
20代やその後訪れる30代では、出産をする可能性があります。
参考までに、厚生労働省が公表している資料「出産費用の状況等について」によると、令和6年度(2024年度)上半期における正常分娩の場合の出産費用の合計額の平均値は517,952円でした。
また、出産をすればその後は子育てが待っているため、子育てや子どもの教育に掛かる費用なども準備していかなければなりません。
住宅の購入
20代やその後の30代では、マイホームの購入を検討する人も多いでしょう。住宅金融支援機構が公表している「2024年度 【フラット35】利用者調査結果」によると、フラット35の利用者によるマイホーム取得資金の平均値は、それぞれ次のとおりでした。
| 融資区分(建て方) | 所要資金 |
|---|---|
| 注文住宅 | 3,936万円 |
| 土地付注文住宅 | 5,007万円 |
| 建売住宅 | 3,826万円 |
| マンション | 5,592万円 |
| 中古戸建 | 2,573万円 |
| 中古マンション | 3,033万円 |
住宅の購入にはローンを組むことが多いため、これらがすべて一時金として必要となるわけではありません。しかし、当然ながらローンはその後返済していく必要があるうえ、購入額の15%程度は頭金を用意すべきことが一般的です。そのため、20代のうちから計画的に貯金をすることをお勧めします。
20代で貯金300万円を達成するポイント
20代で貯金300万円を達成するには、どのようなポイントを押さえれば良いのでしょうか?ここでは、20代で貯金を成功させる主なポイントを4つ解説します。
- 家計の収支を把握する
- 固定費を見直す
- NISAやiDeCoなどを活用して資産形成をする
- プロに相談する
家計の収支を把握する
1つ目のポイントは、まず家計の収支を把握することです。
現在の体重を知らなければダイエットを成功させるのが難しいのと同様に、現在の家計の状態が分からなければ貯金を成功させるのは困難です。そのため、まずは現在の家計の収支を把握することから始めましょう。
- 現在、手取り収入はいくらあるのか
- 毎月、何にどのくらいのお金を使っているのか
- 現在、1ヶ月あたりいくらの貯金ができているのか
などを把握することで、現在の家計の問題点が浮き彫りとなり、具体的な改善につなげやすくなります。
固定費を見直す
2つ目のポイントは、固定費を見直すことです。
家計の支出は、「固定費」と「変動費」に分類できます。固定費とは、毎月おおむね定額の支出となる項目です。
たとえば、住居費や携帯電話料金、水道光熱費、子どもの保育料、サブスクなどが固定費に該当します。一方で、変動費とは娯楽費や食費などのように、毎月金額が変動する支出項目です。
家計を改善して計画的な貯金を実現するには、まず固定費を見直すことをお勧めします。固定費の見直しの効果はその時限りではなく、ある程度継続するためです。
具体的には、次の見直しなどを検討すると良いでしょう。
- 使用頻度の低いサブスクの解約
- 携帯電話会社・携帯電話料金の見直し
- 電力会社・電気料金プランの見直し
- 自動車関連費の見直し(自家用車を手放してカーシェアやリースを活用するなど)
固定費を見直すことで家計のスリム化が可能となり、浮いた分の固定費を貯金に回しやすくなります。
NISAやiDeCoなどを活用して資産形成をする
3つ目のポイントは、NISAやiDeCoを活用した資産形成を検討することです。
2025年現在、預貯金の利率は高いとはいえず、預貯金口座で資産を増やすことは困難です。また、預貯金だけでは将来のインフレリスク(物価が上昇し、相対的に資産価値が下がるリスク)への対応も難しいでしょう。
そこで検討したいのが、投資信託などを活用した資産形成です。一般社団法人投資信託協会の定義によると、投資信託とは「投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、運用の専門家が株式や債券などに投資・運用する商品で、その運用成果が投資家それぞれの投資額に応じて分配される仕組みの金融商品」です。
つまり、1社の株式だけに投資するのではなく、運用のプロが適宜投資先の商品を組み合わせて運用してくれる金融商品を指します。1社だけに投資すると、万が一その企業が倒産した際に大切な資産を失ってしまうでしょう。一方で、投資信託では複数の株式や債券などに投資をするため、このようなリスクが分散されます。
また、その具体的な運用先も、投資信託ごとに異なります。たとえば、「日本の上場株式だけに投資するもの」「米国の債券だけに投資するもの」「全世界の上場株式に投資するもの」などがあります。
また、その運用方針も投資信託ごとに異なっており、ベンチマーク(日経平均株価などの運用指数)と連動した成果を目指す「パッシブ運用」や、ベンチマークを上回る成果を目指す「アクティブ運用」などがあります。
自分に合った投資信託を複数見つけて毎月定額を投資することで、インフレリスクにも対応しやすい資産形成が可能となります。そして、これらの資産形成で役立つのが、NISAやiDeCoです。
NISAとは
NISA(少額投資非課税制度)とは、NISA口座内で運用する上場株式や投資信託などの配当金や分配金、売却益にかかる通常20.315%の税金が非課税となる制度です。非課税で運用できるため、税金分が目減りする事態が避けられ、効率的な資産形成が可能となります。
なお、2025年現在、上場株式や投資信託などが広く対象となる「成長投資枠」と、長期の積立・分散投資に適するとして金融庁の基準を満たした投資信託に毎月一定額を少しずつ投資する「つみたて投資枠」が設けられています。
iDeCoとは
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、自分が拠出した掛金を自分で運用し、資産形成をする年金制度です。掛金の拠出は原則として65歳になるまで可能であり、原則として60歳以降に老齢給付金が受け取れます。
iDeCoの運用先としては定期預金や保険なども用意されているものの、長期の資産形成に適した投資信託がよく選ばれています。掛金の拠出時や運用益が生じた際、老齢給付金を受け取る際などに税制上の優遇措置が設けられているため、効率的な資産形成に役立ちます。
参照元:iDeCoではどうして投資信託が選ばれているの?(iDeCo公式サイト)
プロに相談する
4つ目のポイントは、プロに相談することです。プロに相談することで自分にとって必要な貯金額が算定しやすくなるほか、家計の改善方法や具体的な貯金の方法などについてもアドバイスが受けられます。
自分たちだけでは気づきづらい問題点や改善点も見つけやすくなりモヤモヤの解消につながるため、一度相談してみることをお勧めします。
20代で貯金についてお悩みの際は、ハレノヒハレまでお気軽にご相談ください(ご相談したいことがございましたら「お問い合わせ」フォームからご入力をお願いいたします)。
20代で無理なく貯金を続けるポイント
20代で無理なく貯金を続けるには、どのようなコツがあるのでしょうか?ここでは、20代で無理なく貯金を続ける主なポイントを3つ解説します。
- 貯金したい額を予め別の口座に移す
- 貯金をする目的を明確にする
- 家計簿をつけて定期的に家計の状況を確認する
貯金したい額を予め別の口座に移す
1つ目は、貯金したい額を予め別の口座に移すことです。
「必要なお金を使って、残った分を貯金に回す」という方法では、貯金を続けるのは容易ではないでしょう。なぜなら、このような方法では、貯金に回したい部分のお金についても気軽に使ってしまいやすいためです。
そうではなく、収入が得られたら、貯金したい金額を先に別の口座に移すことをお勧めします。貯金したい額を先に定期預金やNISA口座などの別口座に移すことで、貯金することが「仕組み化」され、無理なく貯金を続けやすくなります。
貯金をする目的を明確にする
2つ目は、貯金をする目的を明確にすることです。貯金をする目的が明確でなければ、貯金を続けるのは容易ではないでしょう。
たとえば、次のような目的を定めることでモチベーションが向上し、貯金を継続しやすくなります。
- 〇歳で結婚をするために、結婚式と新婚旅行、新居への移転の費用として300万円を貯める
- 〇年後に新しい車を買うために300万円を貯める
- 子どもの教育にはお金がかかるので、〇年後までに300万円を貯める
家計簿をつけて定期的に家計の状況を確認する
3つ目は、家計簿をつけて定期的に家計の状況を確認することです。
貯金が思ったように貯まらない場合には、家計簿をつけることをお勧めします。家計簿をつけることで「何にいくらお金を使ったのか」が明確になり、自分の支出状況を客観的に確認しやすくなります。
これにより、たとえば「食費が多い」と感じたら外食の回数を減らしたり、「使っていないサブスクがある」ことに気付いたらこれを解約したりするなど、家計の見直しがしやすくなるでしょう。家計を見直し、家計に余裕が生まれると、貯金を無理なく続けやすくなります。
また、家計簿は家計の「成績表」でもあるため、家計簿をつけて結果を「見える化」することで、貯金を続けるモチベーションにもつながります。
20代の貯金に関するよくある質問
最後に、20代の貯金に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
20代から貯金は必要?
可能な限り、貯金は20代から始めることをお勧めします。なぜなら、20代では近い将来に結婚や出産、マイホームの購入など多くのライフイベントが控えていることが多いためです。
いざお金が必要となった際に後悔しなくて済むよう、無理のない範囲で貯金をすると良いでしょう。
20代の月々の貯金額はどのように決めれば良い?
20代で月々貯金すべき額は、目標額からの「逆算」で決めることが原則です。
たとえば、10年後までに300万円を貯めたいのであれば、1ヶ月あたりの目標貯金額は単純計算で25,000円です。同様に、5年後に500万円を貯めたいのであれば、1ヶ月あたりの目標貯金額は約83,000円となるでしょう。
目標額が高過ぎて、現在の収入ではその金額の貯金が現実的でない場合には、目標額を引き下げることや貯めるべき時期を後ろにズラすこと、収入を増やすことなども検討します。
とはいえ、目標が明確ではなく、この方法では貯金の目標額の算定が難しい場合もあるでしょう。その場合には、「手取り収入の10%」を1つの目安として貯金を始めることも1つの方法です。
まとめ
20代の貯金額に関するデータを紹介するとともに、20代で貯金300万円が少ないのか否かや、20代で備えたいライフイベント、20代で貯金を成功させるポイントなどを解説しました。
20代で貯金300万円が少ないか否かは、独身であるか既婚であるか、子どもはいるのか、理想とするライフスタイルはどのようなものであるのかなどによって異なります。そのため、平均値や他者の貯金額を意識するのではなく、まずは自分や家族にとって必要となる貯金額を算定することから始めるのがお勧めです。
20代で貯金を成功させるポイントとしては、家計の収支を把握して固定費を見直すことや貯金したい額を先に「天引き」して別口座に移すこと、iDeCoやNISAなどを活用すること、プロに相談することなどが挙げられます。プロに相談することで自分の理想の将来を実現するために必要な貯金額が把握しやすくなるほか、自分に合った貯金方法も見つけやすくなるでしょう。
ハレノヒハレは「未来すべて、ハレになれ。」をコンセプトに、家計の見直しや資産形成のサポートをしています。家賃をはじめ生活費全般について相談したいという際は、ハレノヒハレまでお気軽にご相談ください(ご相談したいことがございましたら「お問い合わせ」フォームからご入力をお願いいたします)。