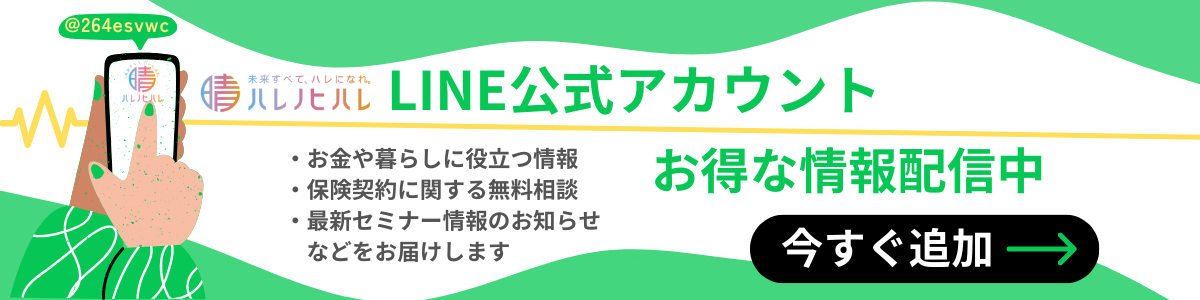お金を育てるという考え方|長期で築く資産形成の基本と主な方法・注意点をわかりやすく解説

長期的な視点で資産形成をするには、「お金を育てる」という考え方を知っておくとよいでしょう。収入を得ることと並行してお金を育てていくことで、より効率的な資産形成が実現しやすくなります。
では、「お金を育てる」方法としては、どのようなものが挙げられるのでしょうか?また、お金を育てようとする場合、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?今回は、お金を育てる方法を紹介するとともに、お金を育てる際の注意点や「お金を育てる」以外の資産形成の方法などについてくわしく解説します。
ハレノヒハレは「未来すべて、ハレになれ。」をコンセプトに、資産形成や家計改善などのサポートをしています。資産形成についてプロに相談したいとお考えの際などには、ハレノヒハレまでお気軽にご相談ください(ご相談したいことがございましたら「お問い合わせ」フォームからご入力をお願いいたします)。
お金を増やす3つの方法
はじめに、お金を増やす3つの方法について概要を解説します。
- 収入を増やす
- 支出を減らす
- お金を育てる(資産形成)
収入を増やす
お金を増やす王道の方法は、収入を増やすことです。収入を増やす方法としては、昇給を目指すことや、副業を始めることなどが検討できます。
支出を減らす
お金を増やすには、「使うお金を減らす」方法も有効です。出ていくお金を減らすことで、手元にお金が残りやすくなるためです。
お金を育てる(資産形成)
お金を増やしたい場合、お金を育てる(資産形成をする)ことも検討するとよいでしょう。お金を育てることで、働くことなどによって得たお金をより効率的に増やしやすくなります。
また、お金を育てることで、インフレリスク(物価が上昇することで、自身の保有資産が相対的に目減りするリスク)にも対応しやすくなります。お金を育てる具体的な方法については、後ほど改めて解説します。
ハレノヒハレは「未来すべて、ハレになれ。」をコンセプトに、資産形成や家計の見直しなどのサポートをしています。将来に備えた資産形成をご検討の際には、ハレノヒハレまでお気軽にご相談ください(ご相談したいことがございましたら「お問い合わせ」フォームからご入力をお願いいたします)。
「お金を育てる」主な方法
「お金を育てる」には、具体的にどのような方法があるのでしょうか?ここでは、主な方法を4つ解説します。
株式投資
1つ目は、株式投資です。株式投資とは、株式会社が発行する株式を購入し、その売却益や配当金によって利益を得る投資方法です。
会社は、投資された資金を元手に事業を展開し、利益を上げることを目指します。資産運用の一環で株式投資をする場合、投資先は上場会社の株式となることが一般的です。
「その企業で使用できる商品券」などの優待が受けられることもあるため、まずは身近な企業の株式への投資から始めることも1つでしょう。
投資信託
投資信託は、投資家から集めた資金を専門家が株式や債券などに分散投資し、その成果を投資額に応じて享受できる仕組みの金融商品です。(出典:一般社団法人 投資信託協会)
投資の格言として、「1つのカゴに卵を盛るな」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。これは、「1つのカゴに卵を盛れば、万が一そのカゴが落下した際に卵がすべて台無しになる」ことを意味し、すなわち「1社だけに集中して投資をすれば、その企業の株が暴落した際に大きな痛手を負う」ことを指します。つまり、分散投資の重要性を表す言葉です。
とはいえ、よほど潤沢な投資資金がある場合を除き、多くの企業の株式や債券に個々に投資をするのは容易ではないでしょう。そこで検討したいのが、投資信託の購入です。
投資信託では、その商品ごとに「日本の上場株式だけ」「世界の上場株式にバランスよく」「米国(アメリカ)の債券だけ」などの一定の「縛り」の中でプロが投資先の商品を選び、小口で販売しています。つまり、1つの投資信託を購入するだけでも、自動的に分散投資ができるということです。
また、「日本の上場株式だけ」に投資をする投資信託と「米国の上場株式だけ」に投資する投資信託を両方購入することで、日本の上場企業(のうち、プロが選んだ複数の企業)と米国の上場企業(のうち、プロが選んだ複数の企業)に少しずつ投資している状態となり、さらなるリスク分散が可能となります。
そして、日経平均株価などの運用指標(「ベンチマーク」と言います)に連動した運用成果を目指す「パッシブ運用」やベンチマークを上回る運用成果を目指す「アクティブ運用」などそれぞれの投資信託に異なる運用方針があるため、これも踏まえて自身に合った商品を選択できます。
なお、NISAやiDeCoなどの制度を活用することで税制の優遇措置が受けられるため、より効率的な資産形成が可能となります。
NISA
NISA(少額投資非課税制度)とは、株式や投資信託の売却益や配当金・分配金にかかる通常20.315%の税金が非課税となる制度です。税金分の資産の「目減り」を避けられることで、より効率的な資産形成が実現しやすくなります。
NISAには、次の2種類があります。
- 成長投資枠:上場株式や投資信託などへの単発での投資などが対象となる
- つみたて投資枠:長期の積立・分散投資に適するとして金融庁の基準を満たした一定の投資信託を定期的に購入する
これらの枠は併用でき、つみたて投資枠は毎月100円や1,000円などの少額から始められるため、これまで投資に馴染みのない方は、まずは少額の積み立てから始めてみるとよいでしょう。
iDeCo
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、自分で作る年金制度です。自分が拠出した掛金を自分で運用し、将来の年金の原資となる資産形成を行います。iDeCoによって積み立てた資金は、原則として60歳以降に老齢給付金として受け取れます。
iDeCoでは、掛金の拠出額が所得控除の対象となるほか、運用益の発生時や給付金の受取時にも一定の税制上の優遇措置が受けられます。老後資金の形成には、iDeCoの活用を検討するとよいでしょう。
不動産投資
3つ目は、不動産投資です。不動産投資とは、不動産を購入し、その不動産を賃貸したり転売したりすることで収益を得る投資手法です。
代表的な不動産投資には、マンションの1室を購入してこれを賃貸することで賃料収入や数年後の売却益の獲得を目指す方法のほか、所有する土地上にアパートを建築して賃料収入を得る方法などが挙げられます。
不動産投資はうまくいけば安定的な「賃料収入」が得られる可能性がある反面、リスクも小さくありません。不動産投資は一定額を金融機関から借り入れて行う場合も多く、想定したように入居者が入らなかったり想定よりも低い賃料でしか入居者が獲得できなかったりすれば、借入金が返済できなくなるおそれもあります。
そのため、不動産投資をする際はリスクを正しく把握したうえで、投資先となる不動産を慎重に見極めるべきでしょう。
金投資
4つ目は、金投資です。金投資とは、金(ゴールド)に投資をして、値上がり益の獲得を目指す投資手法です。
金は世界情勢が不安定な場合でも価値が下がりづらいと言われており、安定的な資産形成に適していると考えられています。
金投資の方法には、金地金(いわゆる「インゴット」や「ゴールドバー」)や金貨に投資をして金庫などで現物を保管する方法のほか、毎月少額ずつ現物の金を積み立て購入する「純金積立」や、金の価格に連動する金投資信託に投資する方法などがあります。
金の現物には盗難リスクがあることから貸金庫の契約などのコストがかかる反面、現物を持っておきたいと考える人も少なくありません。それぞれのメリットやリスクを把握したうえで、自分に合った方法を選択するとよいでしょう。
お金を育てるために知っておきたい「単利」と「複利」の違い
お金を育てる際に知っておくべき知識の1つに、「単利」と「複利」の違いがあります。お金を育てるには、原則として「複利」の方が効率的です。ここでは、単利と複利について、それぞれ概要を解説します。
単利とは
単利とは、元本のみに利息が付く仕組みです。たとえば、5%の利率で100万円を5年間、単利で運用する場合、それぞれの年における利息は、次のようになります。
| 年数 | 利息額 | 計算方法 |
|---|---|---|
| 1年目 | 5万円 | 100万円×5% |
| 2年目 | 5万円 | 100万円×5% |
| 3年目 | 5万円 | 100万円×5% |
| 4年目 | 5万円 | 100万円×5% |
| 5年目 | 5万円 | 100万円×5% |
| 5年経過後の資産額 | 125万円 | 100万円+(5万円×5年) |
単利の場合には利息分には利息は付かないため、初年度の利息も5年目の利息も同じ額となっています。
複利とは
複利とは、運用によって得た利息が元本に組み込まれ、その合計金額をベースに利息が計算される仕組みです。たとえば、5%の利率で100万円を5年間、複利で運用する場合、これにより得られる利息は次のようになります。
| 年数 | 利息額 (円未満切捨て) | 計算方法 |
|---|---|---|
| 1年目 | 5万円 | 100万円×5% |
| 2年目 | 5.25万円 | (100万円+5万円)×5% |
| 3年目 | 5.5125万円 | (100万円+5万円+5.25万円)×5% |
| 4年目 | 5.7881万円 | (100万円+5万円+5.25万円+5.5125万円)×5% |
| 5年目 | 6.0775万円 | (100万円+5万円+5.25万円+5.5125万円+5.7881万円)×5% |
| 5年経過後の資産額 | 127.6281万円 | 100万円+5万円+5.25万円+5.5125万円+5.7881万円+6.0775万円 |
単利と同じく元手が100万円、5%の利率であったとしても、単利と複利とでは2万円以上もの差が生じます。資産形成にあたっては複利の方が効率的であるため、複利での運用を検討するとよいでしょう。
「お金を育てる方法」の注意点
お金を育てることには、注意点もあります。ここでは、お金を育てようとする際に知っておくべき注意点を4つ解説します。
- それぞれに異なるリスクがある
- 元手となるお金が必要となる
- お金を増やすには長期的な視点が必要である
- 確定申告が必要となる場合がある
それぞれに異なるリスクがある
お金を育てる方法には、それぞれ異なるリスクがあります。お金を育てようとする際は、その金融商品のよい面だけを見るのではなく、リスクを正しく把握したうえで投資判断をする必要があります。
なお、投資の世界において「リスク」は「危険」だけを指すのではなく、「不確実性」を意味します。つまり、リスクが低い金融商品は資産が目減りする危険も少ない代わりに、得られるリターンも少ないということです。リスクが低い金融商品の代表格は普通預金であることを踏まえると、イメージが湧きやすいでしょう。
一方で、リスクの高い商品は資産が目減りする危険がある一方で、大きなリターンを得られる可能性もあります。たとえば、株式投資は資産が増える可能性がある一方で、資産が目減りする可能性も低くありません。
このように、「お金を育てる」方法には、その裏返しとしてリスクは付きものです。「お金を大きく増やせるが、資産が目減りするリスクはない」ような金融商品はないため、まずはこの点を正しく理解しておきましょう。
元手となるお金が必要となる
植物を育てるにはその元となる苗木などが必要になるのと同様に、お金を育てるには一定の元手が必要です。元手となるお金が十分にあれば、お金を育てる方法の選択肢も増やしやすいでしょう。
なお、必ずしも高額な元手が必要なものばかりではなく、たとえばNISAであれば月100円や1,000円程度の投資から始められる可能性があります。元手が多くない場合、まずは少額の投資から始めてみるのも1つの方法です。
お金を増やすには長期的な視点が必要である
お金は一朝一夕に増やせるものではなく、ある程度長期的な視点が必要です。「来月までに、元手の100万円を倍の200万円にしよう」などの考えは投資というよりもギャンブルに近いものであり、長期的な資産形成には向きません。また、お金を育てる中で一時的に資産が目減りする場合もあり、その際に必要以上に慌てないことも肝要です。
お金を育てるには短期的な視点で考えるのではなく、まさに「育てる」という言葉どおり、メンテナンスをしつつ少しずつコツコツと形成していくイメージを持っておくとよいでしょう。
確定申告が必要となる場合がある
原則として、所得税では、給与所得者の雑所得等が年間20万円以下なら確定申告が不要となる特例があります(ただし上場株式等の譲渡益・配当は別枠)。上場株式や投資信託の利益は、特定口座(源泉徴収あり)なら原則として確定申告は不要、源泉徴収なしの場合は申告が必要です。住民税は取り扱いが異なることがあるため、迷う場合は所轄の税務署や自治体に確認してください。NISA口座内の利益・分配金は非課税です。
ただし、NISA口座や特定口座内での株式や投資信託の譲渡益などは、たとえ年間20万円を超えても確定申告は必要ありません。NISA口座内で生じた売却益などは非課税であり、特定口座では自動的に源泉徴収がされるためです。
確定申告の要否について判断に迷う際は、管轄の税務署などに事前に相談しておくとよいでしょう。
「お金を育てる方法」以外のお金の増やし方
冒頭で解説したように、お金を増やす方法には、「お金を育てる」以外の方法も存在します。ここでは、「収入を増やす」ことでお金を増やす方法を6つ解説します。
- 昇給を目指す
- 資格手当などの獲得を目指す
- 転職する
- 副業をする
- 独立・起業する
- 権利収入の獲得を目指す
昇給を目指す
1つ目は、昇給を目指す方法です。
現在勤務している企業で昇給を目指すことで、将来へ向かって収入を安定的に増やすことが可能となります。昇給をして安定的な収入アップを目指すことで「お金を育てる」ための元手も増え、効率的な資産形成がしやすくなるでしょう。
上司などに相談して昇給のために「現在、自分に不足している能力・実績」などが把握できれば、具体的な努力の方向が見えやすくなるかもしれません。
資格手当などの獲得を目指す
2つ目は、資格手当などの獲得を目指すことです。企業によっては、業務に役立つ資格を取得した場合に、基本給に上乗せして資格手当が支給される場合があります。
たとえば、「社会保険労務士資格を取得したら月2万円の手当支給」「危険物取扱者の乙種に合格したら月5,000円の手当支給」などです。対象となる資格や手当の額などは企業によって異なるため、勤務先の就業規則や賃金規程などを確認し、手当の支給対象となる資格獲得を目指すとよいでしょう。
転職する
3つ目は、現在の勤務先よりも条件のよい企業に転職することです。転職をすることで給与のアップが期待できれば、より効率的な資産形成が実現しやすくなります。
とはいえ、転職により給与が下がる可能性があるほか、たとえ給与はよくても社風が合わずに後悔する事態も否定できません。そのため、転職は給与以外の条件や企業風土、「自分のやりたい仕事に従事できそうか否か」なども踏まえ、慎重に検討すべきでしょう。
副業をする
4つ目は、副業をすることです。副業をすることで、本業の収入の他にプラスアルファの収入を得ることが可能となります。
夜間や休日に他の企業でアルバイトなどをする方法のほか、フリーランスとして仕事を得る方法などもあるため、自分に合った副業を検討するとよいでしょう。
ただし、企業によっては就業規則などで副業を禁じている場合もあるほか、副業について事前承認制をとっている場合もあることに注意が必要です。このような規定があるにもかかわらず勤務先に無断で副業をすれば、発覚した際に懲戒解雇の対象となるなど、むしろ収入が減る事態を招きかねません。
独立・起業する
5つ目は、独立・起業をする方法です。他者に提供できる技術や能力、ビジネスアイデアがある場合などには、独立・起業によって収入アップを目指すことも1つの選択肢となります。
ただし、独立・起業をすれば、会社員のように安定的な収入の保障はなくなります。ビジネスがうまく軌道に乗れば収入を増やせる可能性がある一方で、収入が減るおそれもあるでしょう。また、独立・起業をすれば、これまで会社が用意してくれていた名刺やパンフレットなどの備品もすべて自分で用意しなければなりません。
独立・起業にはリスクもあるため、まずは副業としてフリーランスとして活動し、起業後の感触をある程度掴んでから全面的に独立することも検討するとよいでしょう。
なお、独立後は病気やけがにより働けなくなったとしても、会社員であれば受けられる「傷病手当金」などの制度は原則として適用されません。そのため、就業不能保険などへの加入など、万が一の収入減少に備える対応の検討もお勧めします。
権利収入の獲得を目指す
6つ目は、権利収入の獲得を目指す方法です。
たとえば、発明や考案をして特許権や実用新案権などの権利を取得し、これを実施したい企業にライセンスすることでライセンス料を得ることなどがこれに該当します。また、イラストや写真などの著作物を創作し、使用の対価としてライセンス料を得ることなども検討できます。
「お金を育てる方法」に関するよくある質問
最後に、お金を育てる方法に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
iDeCoとNISAは併用できる?
iDeCoとNISAは、併用できます。両者を併用することで、税負担を抑えつつ、より効果的な資産形成が実現しやすくなります。
ただし、掛金や積立金が家計を圧迫しないよう、無理のない拠出を検討すべきでしょう。
投資でよく聞く「ドルコスト平均法」とは?
「ドルコスト平均法」とは、価格が変動する金融商品について定期的に定額を買い増す投資手法です。たとえば、ある投資信託を「その時の価格に関わらず、毎月25日に1万円ずつ購入する」場合などがこれに該当します。
購入時にその金融商品の価格が高ければ、購入できる数量(口数)は少なくなります。一方で、購入時にその金融商品の価格が低ければ、購入できる数量(口数)は多くなります。
金融商品の価値は随時変動するものの、ドルコスト平均法を活用することで平均購入単価を平準化でき、長期的な資産形成に役立つと考えられています。
まとめ
お金を育てる方法を紹介するとともに、お金を育てる際の注意点や「お金を育てる」以外の資産の増やし方などを解説しました。
お金を増やす方法としては、収入を増やすことや支出を減らすことのほか、お金を育てることによる資産形成が挙げられます。そして、お金を育てる主な手法には、株式投資や投資信託、不動産投資、金投資などがあります。
お金を育てることには投資をする商品ごとに異なるリスクがあるため、リスクを正しく把握したうえで自分に合った方法を選択するとよいでしょう。また、お金を育てるには短期的な視点で見るのではなく、長期的な視点で考えることをお勧めします。
ハレノヒハレは「未来すべて、ハレになれ。」をコンセプトに、資産形成や家計の見直しなどのサポートをしています。将来へ向けた資産形成についてプロへの相談をご希望の際などには、ハレノヒハレまでお気軽にご相談ください(ご相談したいことがございましたら「お問い合わせ」フォームからご入力をお願いいたします)。