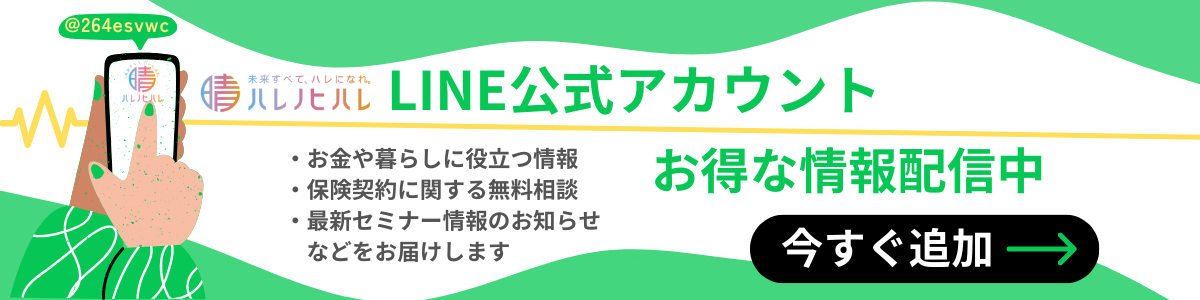学資保険に入りそびれたらどうする?加入の必要性と他の方法について解説
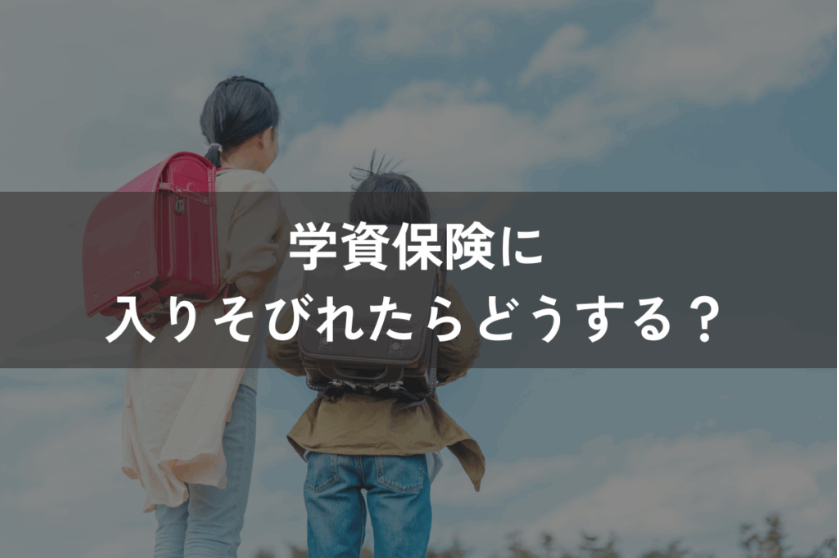
子どもの教育資金の準備方法として、一般的に良く選ばれているのが「学資保険」です。ただし、学資保険には子どもの加入時の年齢に制限があります。なかには、学資保険に入りそびれた人もいるのではないでしょうか?
学資保険に入りそびれた場合でも、子どもの教育資金の確保の選択肢は数多く存在します。そこで今回は、学資保険の加入の必要性や他の方法についてくわしく解説します。
なお、ハレノヒハレは「未来すべて、ハレになれ。」を信念として、ファイナンシャルプランナーがライフスタイルに合わせてアドバイスいたします。学資保険についてお悩みの際は、ハレノヒハレまでお気軽にご相談ください(ご相談したいことがございましたら「お問い合わせ」フォームからご入力をお願いいたします)。
学資保険の概要と特徴
そもそも、学資保険とはどのような保険なのでしょうか?ここでは、学資保険の概要と特徴について解説します。
学資保険とは
学資保険は、主に子どもの教育資金準備を目的に設計された、貯蓄性のある生命保険です。保護者である親が契約者になって加入し、子どもの進学など節目のタイミングで祝金や満期保険金を受け取ることができます。
また、多くの商品では契約者が死亡または高度障害状態になった場合、以後の保険料は免除されます。保険料が免除されても満期保険金は予定通り受け取れるため、親に万一があっても子どもの教育費用を残してあげることができます。
学資保険に加入できるのは、一般的には「子どもの年齢が7歳になるまで」です。学資保険の種類によっては子どもが12歳になるまで加入できたり、出生前から加入できたりする商品もあります。
学資保険の特徴
学資保険には、どのような特徴があるのでしょうか?ここでは、主な特徴を解説します。
- 計画的に教育資金を準備できる
- 万一のときの子どもの学費を確保できる
- 生命保険料控除が受けられる
計画的に教育資金を準備できる
1つ目の特徴は、計画的に教育資金を準備できる点です。
学資保険は、契約時に祝金や満期保険金の受取金額を決めておき、毎月所定の保険料を払い込んで積み立てていくことが一般的です。払い込んだ保険料を自由に引き出すことができないため、契約期間中は確実に教育資金を積み立てられます。預貯金と異なり、途中でほかの用途にお金を使ってしまう心配はありません。
また、返戻率が100%以上になれば、払い込んだ保険料の総額よりも受け取れる祝金、満期保険金の総額が多くなります。
万一のときの子どもの学費を確保できる
2つ目の特徴は、万一のときの子どもの学費を確保できる点です。
学資保険には、多くの商品に「保険料払込免除特約」が付帯しています。保険料払込免除特約とは、契約者(親)が死亡または高度障害状態になった場合、それ以降の保険料の払い込みが免除される仕組みです。
預貯金でも教育資金を貯めることは可能ですが、契約者に万一があると貯蓄の継続が難しくなります。学資保険なら、契約者に万一があっても当初計画した祝金や満期保険金の受け取りが可能です。
学費の準備と万一のときの保障の両方を準備できるのは、学資保険ならではの特徴といえます。
生命保険料控除が受けられる
3つ目の特徴は、生命保険料控除が受けられる点です。
学資保険に加入して保険料を払い込むと、年末調整や確定申告の際に生命保険料控除が受けられます。生命保険料控除には次の3つの区分があり、学資保険は「一般生命保険料控除」に該当します。
- 一般生命保険料控除
- 介護医療保険料控除
- 個人年金保険料控除
生命保険料控除が適用されると、払い込んだ保険料の一定金額が課税所得から差し引かれ、所得税や住民税が契約者の税率分だけ軽減されます。
学資保険の必要性とは?
学資保険に入りそびれた場合でも、急いで加入するのが良いとは限りません。ここでは、子どもに必要になる教育費用の目安と、学資保険の留意点について解説します。
子どもの教育費の目安
文部科学省によると、幼稚園から大学までにかかる費用を合計すると下の表のようになります。
| 在学期間の学習費総額 | |
|---|---|
| 公立幼稚園 | 472,746円 |
| 公立小学校 | 2,112,022円 |
| 公立中学校 | 1,616,317円 |
| 公立高等学校(全日制) | 1,543,116円 |
| 合計 | 5,744,201円 |
| 在学期間の学習費総額 | |
|---|---|
| 私立幼稚園 | 924,636円 |
| 私立小学校 | 9,999,660円 |
| 私立中学校 | 4,303,805円 |
| 私立高等学校(全日制) | 3,156,401円 |
| 合計 | 18,384,502円 |
| 在学期間の学習費総額 | |
|---|---|
| 国公立大学 | 4,812,000円 |
| 私立大学(文系) | 6,898,000円 |
| 私立大学(理系) | 8,216,000円 |
参照元:令和3年度 教育費負担の実態調査結果(日本政策金融公庫)
私立を選択した場合は、幼稚園から高等学校まで2,000万円近い学費を支払いつつ、別途700万円~800万円の学費を用意する必要があります。
学資保険の留意点
教育費用の準備に約4割の人が加入している学資保険ですが、留意点をおさえておきましょう。学資保険の主な留意点は以下のとおりです。
- 低金利の環境では資産が増えにくい
- 中途解約すると元本割れの可能性が高い
- 急な出費への対応ができない
- インフレリスクがある
このように、学資保険にはさまざまな留意点があります。留意点をふまえて教育資金を準備するには学資保険以外の検討が必要ですが、どの商品が自分に合っているかの判断は難しいものです。
自身に合った的確な教育資金の準備方法を選択するため、ハレノヒハレまでお気軽にご相談ください(ご相談したいことがございましたら「お問い合わせ」フォームからご入力をお願いいたします)。
低金利の環境では資産が増えにくい
学資保険で払い込んだ保険料の総額に対して、受け取れる金額の割合を表したものが「返戻率」です。「返戻率100%」とは、払い込んだ保険料と同額を受け取れるケースです。
一般的に、満期保険金を受け取るまでの期間が長いほど保険料を長く運用でき、返戻率は高くなります。
ただし、昨今の低金利な状況下では10年以上保険料を払い込んでも、資産を大きく増やすことは難しいのが実情です。たとえば、返戻率105%の商品の場合は約190万円の保険料を支払うと、満期までに200万円の満期保険金を受け取れるというイメージです。
子どもの大学費用が400万円以上かかる可能性をふまえて、より積極的に資産形成を検討するのも選択肢の1つといえるでしょう。
中途解約すると元本割れの可能性が高い
学資保険は、加入してから満期を迎えるまでに徐々に返戻率が上昇します。払い込んだ保険料の総額よりも多い祝金・満期保険金を受け取れるのは、長期間(できれば満期まで)保険料を払い込んで解約しなかった場合です。
満期を待たずに中途解約した場合は解約返戻金を受け取れますが、返戻率が100%を下回る可能性があります。100%未満の返戻率は払い込んだ総額より解約返戻金が低くなることを示しているため注意が必要です。
つまり、家計収入の低下などで途中解約すると払い込んだ保険料の一部が戻ってこず、元本割れになる可能性があります。
急な出費への対応ができない
急な出費への対応が難しいのは、学資保険の留意点の1つです。金融機関の普通預金は任意のタイミングでお金を引き出せますが、学資保険は払い込んだ保険料を自由に出金できません。
祝金や満期保険金を受け取るタイミングは加入時に定めるため、他のタイミングで払い込んだ保険料を引き出すには解約手続きが必要です。中途解約には元本割れのリスクがあり、教育資金の準備ができなくなる可能性もあります。
払い込んだお金を急な出費で出金すると想定される場合、普通預金など、短期で現金化できる方法が適しているでしょう。
インフレリスクがある
学資保険は、インフレリスクという留意点があります。インフレとは、物価の上昇によって相対的にお金の価値が目減りすることです。
学資保険の契約時に決めた満期保険金の金額は、物価がどれだけ上がっても変わりません。将来的にインフレが起こって物価が2倍になったと仮定すると、受け取れる祝金や満期保険金の価値が半減する可能性もあります。
インフレに備え、長期的に教育資金を準備するには、インフレに対応できる方法(商品)を検討することも選択肢の1つです。
学資保険に加入する必要性が低い人の特徴
次のいずれかに該当する場合は、学資保険に加入する必要性が低いといえるでしょう。学資保険に入りそびれたとしても慌てず、他の方法を検討するのがお勧めです。
- すでに子どもの教育費用の準備ができている
- 中途解約をする可能性がある
- 効率的に資産形成を進めたい
- 貯めたお金を任意のタイミングで引き出したい
学資保険の目的は子どもの教育資金の準備であり、すでに教育費用が用意されているなら加入する必要はありません。たとえば、国公立大学の入学費用と学費の合計は平均4,812,000円ですが、貯める目途が立っているなら学資保険での準備は不要です。
また、中途解約するリスクがある場合、学資保険への加入はお勧めできません。
保険料払込期間中に解約すると返戻率は100%を下回るケースが多いので、解約返戻金を受け取っても払い込んだ保険料を下回ります。最後まで保険料を払い込めるか検討が必要で、難しいのであれば他の方法が選択肢になるでしょう。
効率的に資産形成を進めたい人や、お金を任意のタイミングで引き出したい人も同様に、学資保険への加入の必要性は高くありません。効率良く資産形成ができる方法を模索することも選択肢になるかもしれません。
学資保険に入りそびれた場合に検討したいインフレリスクへの対応方法
学資保険に入りそびれてしまった場合、どのような対応方法があるのでしょうか?ここでは、学資保険に入りそびれた場合の主な対応方法を3つ解説します。
- NISAと生命保険(死亡保険)の組み合わせ
- 変額保険
- 外貨建ての生命保険
NISAと生命保険(死亡保険)の組み合わせ
1つ目は、NISAと生命保険(死亡保険)の組み合わせです。
NISAとは、将来に向けた資産づくりを国が支援する少額投資非課税投資制度のことです。通常、投資で得られた利益には20.315%の税金がかかりますが、NISA口座での投資によって得られる『運用益』は非課税保有限度額の範囲内で非課税となります。
| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
| 年間投資枠 | 240万円 | 120万円 |
| 非課税保有限度額 | 1,800万円(成長投資枠は1,200万円) | |
| 非課税保有期間 | 無期限 | |
参照元:NISAを知る(金融庁)
以前は非課税保有期間が5年または20年の期限付きでしたが、2025年9月現在は恒久化されているため、長期の資産形成の手段としてより適しています。
投資対象は日本株式、外国株式、投資信託などさまざまですが、プロが投資家の代わりに運用する投資信託は初心者でも始めやすいでしょう。運用結果によっては、投資した元本を大きく上回る利益を得られることもあります。
ただし、NISAはリスクがある株式や投資信託などへの投資が前提であり、元本の保証はありません。運用結果次第では払い込んだ元金を下回るリスクもあります。預貯金や保険と併用するなど、自身のリスク許容度の範囲内で投資を進めることが大切です。
また、NISA自体には学資保険と違って保障機能がありません。資金の一部を定期保険や終身保険などの死亡保険の保険料の払い込みに回し、万一のときに子どもの学費を準備できるようにしておくことも大切です。
変額保険
2つ目は、変額保険です。変額保険は、将来的に受け取れる保険金等の額が変動する生命保険のことです。
保険会社が保険料の一部を投資信託などで運用し、運用実績によって満期保険金や解約返戻金の金額が変わります。運用実績が良くなれば満期保険金や解約返戻金が増加するため、一般的にインフレリスクに備えることが可能とされています。
また、被保険者が死亡または高度障害状態になった場合は死亡保険金または高度障害保険金が支払われます。なお、一般的には運用実績で金額が変動するのは満期保険金や解約返戻金のみで、死亡保険金や高度障害保険金が基本保険金額を下回ることはありません。
外貨建ての生命保険
3つ目は、外貨建ての生命保険です。外貨建て保険とは、保険料の払い込み、満期金・解約返戻金の受け取りなど、保険に関わる取引を米ドルや豪ドルなどの外貨で行う保険のことです。
日本円よりも金利の高い外貨で運用するため運用利率が高く、円建ての保険と比較して貯蓄性が高い特徴があります。また、円安の環境では受け取れる解約返戻金や満期金が円ベースで高くなるため、さらに返戻率が高くなります。
高い金利のおかげで教育資金などまとまった出費への準備として候補になるでしょう。ただし、円高の時期は解約返戻金や満期保険金を受け取る際に、円ベースで元本割れするリスクがある点には注意が必要です。外貨建ては為替変動や為替手数料等により、円換算額が目減りする可能性があります。解約・受取のタイミングと為替水準に注意が必要です。
学資保険に入りそびれてリスクを許容できない場合の選択肢
前述した「NISA」「変額保険」「外貨保険」には元本割れの可能性があり、リスクを許容できない人にとっては選択肢にならない可能性もあります。一方、リスクを許容できない場合でも、教育費用の準備方法としては例えば次のような選択肢があります。
- 対象年齢の幅が広い学資保険
- 終身保険
- 預貯金
- 個人年金保険
- 個人向け国債
- 奨学金
対象年齢の幅が広い学資保険
学資保険に入りそびれ、元本割れのリスクを許容できない人には、対象年齢の幅が広い学資保険への加入が選択肢になります。
一般的な学資保険の場合、学資保険に加入できるのは「子どもが7歳になるまで」です。一方、なかには7歳を超えても加入できる学資保険もあります。
学資保険の一般的な加入期限である7歳を超えた場合、加入年齢が広い学資保険が選択肢になるでしょう。ただし、子どもが7歳を超えて学資保険に加入する場合は通常の学資保険より保険料払込期間が短くなり、毎月の保険料が高くなります。
終身保険
終身保険とは、一生涯の保障があり、貯蓄性を備えた保険のことです。保険料払込期間終了後は1年経つごとに解約返戻金が増え、払い込んだ総額よりも多くの解約返戻金を受け取れるようになるケースもあります。
また、保険料払込期間中の解約返戻金を抑える代わりに、通常の終身保険よりも保険料を抑えられる「低解約返戻金型終身保険」もあります。終身保険は学資保険と異なり、満期がないことが特徴です。教育資金をほかの手段で準備できれば、解約せずに老後資金の備えにできるでしょう。
預貯金
教育資金の準備でもっとも手軽に始められるのが預貯金でしょう。積み立てたお金は確実に貯まるため、元本割れリスクを避けたい人にお勧めできます。
自由に入出金できる普通預金の場合、家計の状況に合わせて毎月の貯金額を柔軟に調整できることもメリットです。また、定期預金は預けたお金を原則として満期まで引き出せないため、途中で取り崩してしまう心配がありません。
「自動積立定期預金」のように手動で入金せず、毎月定額を自動的に積み立てられる商品もあります。
個人年金保険
個人年金保険とは、契約時に決めた年齢に達するまで保険料を払い込み、その後は終身もしくは一定期間にわたって年金を受け取れる保険のことです。主に老後資金の準備に活用されますが、教育資金の準備にも利用できます。
子どもの進学時期に合わせて満期を設定すれば、必要な時期に資金の確保が可能です。また、契約者が年金を受け取る前に死亡した場合は、払い込んだ保険料に相当する死亡保険金を受け取れることが一般的です。
払い込んだ保険料は個人年金保険料控除の対象となり、一定の条件下で所得控除を受けられます。
個人向け国債
個人向け国債とは、日本国政府が発行する、個人なら誰でも購入できる債券のことです。政府が発行する債券を個人が購入し、対価として定期的に利息を受け取れます。
国が発行しているため安全性が高く、中途換金時は直前2回分の利子相当額が差し引かれますが、原則として元本割れしにくい設計になっています。元本割れのリスクを回避しながら堅実に教育資金を準備したい人にお勧めです。
奨学金
奨学金とは、経済的な理由で修学が困難な学生に対し金銭を給付または貸し付ける制度のことです。主要な団体は日本学生支援機構(JASSO)で、これまで紹介した保険や資産運用と違って学生本人が契約することになります。
JASSOの奨学金には利息の付かない「第一種奨学金」と、利息の付く「第二種奨学金」のほか、給付型もあります。条件を満たせば返済不要で学費の支払いが可能です。
ただし、いずれの奨学金も学力基準に満たないと利用できません。また、申し込める時期が決まっているため、思い立ったらすぐに借りられるものではないことにも注意が必要です。
学資保険に入りそびれた人のよくある質問
最後に、学資保険に入りそびれた人のよくある質問とその回答を2つ紹介します。
学資保険に入るタイミングはいつがベスト?
学資保険に入るタイミングについては、一般的には早ければ早いほど良いでしょう。
学資保険に早期加入すると保険料を払い込む期間が長くなり、毎月払い込む保険料を抑えられます。早期に加入すると、返戻率が上がりやすいというメリットもあります。保険料を運用する期間が長くなって利益が増えやすいためです。
また、産前から学資保険の検討を始めると、夫婦間で話し合う時間がしっかり確保できるのもメリットです。
学資保険は入らない方が良いと聞くけど本当?
「学資保険は入らない方が良い」ということはありませんが、以下の留意点を押さえておく必要があります。
現在の低金利の環境下では資産が増えにくい、中途解約すると元本割れの可能性が高い、急な出費への対応ができない、インフレリスクがある等(詳しくは上記で説明しています)をふまえて検討しましょう。
学資保険に入りそびれてお悩みの際は「ハレノヒハレ」にご相談ください
学資保険に入りそびれた人に向けて学資保険の必要性と他の方法について解説しました。
学資保険は子どもが小学生になった後でも加入できる可能性があります。ただし、「保険料が高くなる」「低金利環境では資産を増やすことは期待しにくい」などの理由で他の方法を検討することも選択肢になりえます。
NISA+生命保険や変額保険、預貯金や終身保険、個人年金保険なども視野に入れ、自身にとって最適な方法になるように考えることが大切です。自分だけで学資保険に入りそびれたときの対策がわからない場合、一人で悩まずにプロに相談しましょう。
ハレノヒハレは「未来すべて、ハレになれ。」をコンセプトとして、お客様一人ひとりの状況やご希望、ライフスタイルなどに合わせたアドバイスを行っています。学資保険に入りそびれてお悩みの際は、ハレノヒハレまでお気軽にご相談ください(ご相談したいことがございましたら「お問い合わせ」フォームからご入力をお願いいたします)。