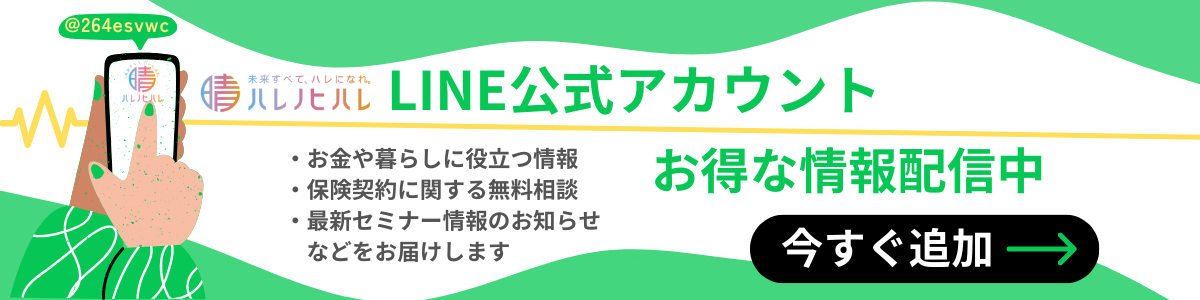介護保険の「必要性」とは?加入のメリット・デメリットと必要な人・不要な人を解説

親のことや、自分の老後のことを考えると、ふと「介護保険は本当に必要?」といった疑問が浮かぶ人も多いでしょう。超高齢社会を迎えた日本では、介護はどの家庭にも訪れうるテーマです。とはいえ、介護保険は種類も多く、公的制度と民間保険の違いもわかりにくいと感じる人も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、介護保険の必要性や公的制度の仕組み、民間保険の役割、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。読み終えるころには「自分や家族にとって必要かどうか」を判断できるヒントがきっと見つかるはずです。
なお、ハレノヒハレは「未来すべて、ハレになれ。」を信念として、保険見直しや家計見直しなどファイナンシャルプランナーがライフスタイルに合わせてアドバイスいたします。介護保険についてお悩みの際は、ハレノヒハレまでお気軽にご相談ください(ご相談したいことがございましたら「お問い合わせ」フォームからご入力をお願いいたします)。
介護保険とは?「公的介護保険」と「民間介護保険」の違い
介護保険には「公的介護保険」と「民間介護保険」があり、両者は役割が異なります。公的保険は全国民が加入する基礎的な制度で、民間保険は不足分を補うために活用する仕組みです。
公的介護保険は、国内居住の40歳以上が対象。65歳以上は原因不問(第1号)、40〜64歳は老化に伴う特定疾病が原因の場合に対象(第2号)。利用は要支援1・2/要介護1〜5の認定が前提となっています。しかし、公的保険だけでは自己負担分やサービスの対象外となる費用をカバーできません。
そこで登場するのが民間の介護保険です。民間の介護保険は、在宅や施設でかかる費用を補てんし、家計や家族の負担を和らげる役割があります。
介護が必要になった場合の自己負担額は、在宅介護で月平均約 2万円〜5万円、施設介護では月額 10万円以上 になるケースも珍しくありません。公的介護保険があっても、自己負担がゼロになるわけではないのです。
この「自己負担分」に備えられるのが民間の介護保険です。給付形式も「一時金型」や「年金型」などがあり、選び方によってはライフスタイルに合わせて介護費用を安心して準備できます。
| 項目 | 公的介護保険 | 民間介護保険 |
|---|---|---|
| 加入対象 | 40歳以上の全国民 | 任意(希望者) |
| 利用条件 | 要介護認定を受けること | 契約条件による |
| 自己負担 | 原則1割(所得で2〜3割)。月ごとの支給限度基準額を超えた利用は全額自己負担。 | 保険契約に基づく給付 |
| 補償範囲 | 基本的な介護サービス | 自己負担分やサービス外費用を補完 |
| 役割 | 最低限の保障 | 不足分のカバー・安心の追加 |
つまり、介護保険を理解する第一歩は「公的保険=基礎」「民間保険=補完」という役割の違いを知ることです。公的制度を前提に、自分や家族にどのくらいの追加保障が必要かを考えることが大切です。
介護保険への加入は必要?
介護保険は、多くの人にとって「必要になる可能性が高い」保険です。なぜなら、日本では高齢化が急速に進み、実際に介護を受ける人が年々増えているからです。
生命保険文化センターの調査によると、令和4年度(2022年度)の民間の介護保険の加入率は9.5%にとどまっており、医療保険や死亡保険に比べて低い水準です。
参照元:生活保障に関する調査/令和4年度(生命保険文化センター)
加入率が低い理由としては、「公的介護保険があるから十分」と考える人が多いこと、介護保険料が比較的高いこと、将来の介護リスクを実感しにくいことなどが挙げられます。しかし、実際には公的介護保険だけでは自己負担が残るため、必要に応じて民間保険で備えることが重要になります。
日本は世界でも有数の超高齢社会で、65歳以上の約19.1%、75歳以上では約 31.0% の人が要介護の認定を受けており、令和5年度(2023年5月〜2024年4月審査分)の介護サービス及び介護予防サービスの年間実受給者数は約663万人(同年度比 +1.7%)にものぼります。つまり、年齢を重ねれば誰もが介護が必要になる可能性が高まるということです。
参照元:
さらに、介護にかかる費用は決して小さくありません。厚労省のデータによると、介護サービスにかかる費用は平均で月額 約20万円前後(サービス全体の総額)ですが、そのうちの一部は自己負担です。公的介護保険があるとはいえ、全額をまかなえるわけではなく、不足分は貯蓄や民間保険で対応する必要があるでしょう。
実際に介護を経験した家庭では、在宅介護なら月に平均5.3万円、施設介護では月に平均13.8万円 程度の自己負担が発生することが多いと報告されています。また、平均介護期間は4. 7年程度 とされ、長期化すればするほど経済的な負担が重くなります。そのため「いざ介護が必要になったとき、貯蓄だけで乗り切れるのか?」という不安を持つ人が増えているのです。
参照元:リスクに備えるための生活設計(生活保険文化センター)
つまり、介護保険を「必要かどうか」と迷う背景には、日本社会全体の高齢化と介護費用の現実があります。公的介護保険制度で最低限は守られますが、十分とはいえないため、多くの人にとって「民間介護保険を含めて検討する必要性」が高まっているのです。
介護保険に加入するメリット
介護保険の最大のメリットは、高額な介護費用の自己負担を軽減し、家計と生活を守れる点でしょう。介護が必要になれば、在宅でも月数万円、施設介護なら月10万円以上の負担が発生することも珍しくありません。
これらの出費は長期化しやすく、貯蓄だけでは対応に限界があります。しかし、民間介護保険に加入しておけば、公的介護保険で不足する部分を補い、将来への安心につなげることができます。
たとえば、介護が5年間続けば自己負担が500万円を超える可能性もありますが、保険の一時金や年金型の給付を活用すれば、貯蓄を大きく取り崩すことなく対応できます。さらに、経済的な支えがあることで、介護を担う家族の精神的な負担も軽減できます。
つまり、介護保険の価値は「経済的備え」だけにとどまらず、「家族の安心」にもつながるのです。
参照元:リスクに備えるための生活設計(生活保険文化センター)
介護保険に加入するデメリット
介護保険にはメリットがある一方で、注意すべきデメリットもあり、すべての人にとって必要とは限りません。
多くの商品は掛け捨て型で、若い頃から長期間保険料を払い続けると負担が膨らみます。
また、医療保険に介護特約を付けている人や、十分な貯蓄がある人にとっては、民間介護保険を追加する必要性は低いケースもあります。
たとえば、毎月5,000円の保険料を30年間払い続けると総額は180万円になりますが、介護を受けなければ全額掛け捨てとなります。このように、介護保険は「安心を買う」代わりにコストを負担する仕組みであることを理解する必要があります。
つまり、介護保険の必要性はライフスタイルや資産状況によって異なるため、自分に本当に必要かどうかを見極めることが欠かせません。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 費用面 | 高額な介護費用に備えられる | 一般的に掛け捨て型で費用負担が重くなる可能性がある |
| 家族への影響 | 経済的・精神的負担を軽減 | 保険料負担が長期化する |
| 給付内容 | 一時金・年金型など選べる | 他の保障と重複する場合あり |
「メリットは魅力的だが、デメリットも気になる」という場合には、中立的な立場から比較検討できるファイナンシャルプランナーへの相談が有効です。自身に合った介護保険を選択するため、まずはハレノヒハレまでお気軽にご相談ください(ご相談したいことがございましたら「お問い合わせ」フォームからご入力をお願いいたします)。
介護保険の「必要性が高い人」と「必要性が低い人」の違い
介護保険は誰にでも必要なわけではなく、資産状況や家族構成によって「加入を検討すべき人」と「急いで加入しなくてもよい人」に分かれます。ここでは、介護保険の「必要性が高い人」と「必要性が低い人」の特徴について解説します。
介護保険の必要性が高い人
介護保険が特に重要となるのは、将来、自己負担だけで介護費用をまかなうのが難しい人です。介護は長期化する可能性が高く、生活費と並行して支払うことになるため、備えがなければ家計への負担が大きくなります。
たとえば、老後資金に不安がある人や、一人暮らしで身近に支援してくれる家族がいない人は、介護保険によって経済的な安心を得られます。また、子どもが遠方に住んでいる場合や、両親・家族の介護を自分が担う可能性がある人も、民間保険で備えておくと安心です。介護は突然始まることが多く、「親が元気だからまだ大丈夫」と考えて準備を先延ばしにすると、いざというときに間に合わないこともあります。
つまり、「老後資金が不十分な人」「一人暮らしや子どもが遠方にいる人」「両親や家族の介護に備えたい人」は、介護保険を検討すべき代表的な対象といえます。
介護保険必要性が低い人
一方で、状況によっては介護保険が不要、あるいは優先度が低い場合もあります。十分な資産や介護特約付きの保険を持っている人は、自己負担で介護費用をまかなえるため、加入しなくても生活を維持できるからです。
具体的には、多額の貯蓄や安定した年金収入がある人、あるいは医療保険や貯蓄型保険で介護リスクをカバーできている人は、民間介護保険の必要性が低いといえます。また、すでに介護施設入居費用を準備している人や、両親・家族の介護を担う予定がなく、自分自身の介護だけを想定すればよい人も優先度は下がります。
つまり、「資産や年金で十分に備えられる人」「既存の保険で介護リスクをカバーしている人」「家族介護の負担を想定していない人」にとっては、介護保険は必ずしも必要ではないのです。
介護保険への加入を検討する際のポイント
介護保険を検討する際に重要なのは、次の3つです。これらを押さえることで「入り損」や「備え不足」を防ぐことができます。
- 加入のタイミング
- 保障内容の確認
- 他の資産形成とのバランス
ここでは、介護保険への加入を検討する際のポイントについて解説します。
1.加入のタイミング
介護保険は40代後半〜50代前半に加入するのが適切とされています。若すぎると長期間保険料を払い続けることになり、負担が大きくなります。一方、60代以降になると健康状態によって加入が難しくなったり、保険料が割高になったりするリスクがあります。
厚生労働省の統計では、要介護認定を受ける割合は65歳以上で19.1%、75歳以上では31.0%に上昇します。このリスクが本格化する前に加入しておくことで「保険料の負担」と「介護リスク」のバランスが取れるのです。
さらに重要なのは、親の介護が現実化する前に備えることです。介護が必要になってからでは加入できない、あるいは条件が厳しくなる場合が多く、経済的負担をすぐに軽減することはできません。実際に民間の介護保険では健康状態の告知が求められ、持病や既に要介護認定を受けている場合には加入が難しいケースもあります。
また、年齢が上がるほど保険料は高くなるため、親の介護が差し迫ってから契約すると割高になるリスクもあります。厚生労働省のデータでは、介護が必要となる平均年齢は男性75歳、女性77歳前後であり、そこから10〜20年前に備えることが合理的です。たとえば50代で加入すれば、比較的低い保険料で将来の安心を確保できます。
つまり、「介護が必要になってからでは遅い」という点が最大の理由です。40代後半〜50代前半のうちに準備しておくことで、経済的にも心理的にも余裕を持って対応できます。まさに「早すぎず、遅すぎず」が賢明なタイミングといえます。
参照元:介護保険制度をめぐる状況について(厚生労働省老健局)
2.保障内容の確認
介護保険を選ぶ際は、給付の仕組みや保障範囲を丁寧に確認する必要があります。「一時金型」「年金型」などの形式によって受け取れる資金の使い道は異なり、在宅介護を重視するか施設介護に備えるかによっても必要な保障は変わります。
在宅介護を想定するなら訪問介護やデイサービスをカバーする保障が有効であり、施設介護を想定するなら長期入所費用に対応できる保障が安心です。また、終身保障か一定期間保障かも重要な判断基準になります。
「自分や家族がどのような介護を望むか」を具体的にイメージし、それに合った保障を選ぶことが大切です。
3.他の資産形成とのバランス
介護保険だけに頼らず、NISAやiDeCo、医療保険などと組み合わせて総合的に備えることが欠かせません。
介護リスクは大きな課題ですが、老後には医療費・生活費・娯楽費など多様な支出があります。介護保険料を優先しすぎて他の資産形成が疎かになれば本末転倒です。
たとえば、NISAで資産運用を行いながら、医療保険で入院リスクをカバーし、介護保険は最低限にとどめるといった組み合わせが有効です。金融庁や厚生労働省も「民間保険は公的制度を補完する役割」と位置づけています。
参照元:公的保険について(厚生労働省)
介護保険は「老後の資産形成の一つの選択肢」として捉え、他の制度と組み合わせて検討することが安心につながります。
自身に合った的確な資産形成方法を選択するため、まずはハレノヒハレまでお気軽にご相談ください(ご相談したいことがございましたら「お問い合わせ」フォームからご入力をお願いいたします)。
介護保険に関するよくある質問
最後に、介護保険に関してよくある質問とその回答を8つ紹介します。
公的介護保険だけで十分ではないですか?
原則、最低限は守られますが、公的介護保険だけでは十分とは言えません。なぜなら、最低限の費用補助にとどまり、実際の介護費用は在宅で月2〜5万円、施設では月10万円以上になることもあるからです。不足分は民間介護保険や貯蓄で補う必要があります。
介護保険は何歳から加入するのがよいですか?
40代後半〜50代前半が目安です。早すぎれば保険料負担が長期化し、遅すぎれば健康状態で加入できない可能性があります。
厚生労働省の統計でも65歳以上で19.1%、75歳以上で31.0%が要介護認定を受けており、リスクが高まる前に加入するのが安心です。
参照元:介護保険制度をめぐる状況について(厚生労働省老健局)
医療保険と介護保険は両方必要ですか?
人によって必要性は異なります。医療保険は「病気やケガの治療費」、介護保険は「介護費用」と対象が違うため、どちらもバランスよく備えることが大切です。ライフプランに応じて優先順位を決めましょう。
「掛け捨て型」と「積立型」どちらが良いですか?
割安にシンプルに備えるなら掛け捨て型、資産形成も重視するなら積立型です。掛け捨て型は短期間で効率的に備えられる一方、積立型は解約返戻金や将来資産も兼ねられます。家計計画や貯蓄状況に合わせて選ぶことが重要です。
保険会社によって介護保険の内容は違いますか?
はい、大きく異なります。給付方法(例:一時金・年金型)、介護度判定の基準、在宅重視か施設重視かなど各社で条件が異なります。同じ「介護保険」でも内容はさまざまなので、複数社を比較することが不可欠です。
親の介護にも自分の介護保険は使えますか?
いいえ、介護保険は契約者本人が要介護状態になったときに給付されるものです。親や家族の介護には直接使えません。
ただし、自分の介護費用を備えておくことで、将来子どもや家族の負担を減らせるため「家族を守る準備」として役立ちます。
介護保険の給付金はどのように受け取れますか?
主に、「一時金タイプ」と「年金タイプ」があります。一時金は施設入居や住宅改修などまとまった費用に、年金タイプは在宅介護など継続的な費用に向いています。
保険会社によって形式が異なるため、事前に自分のライフプランに合った形を確認しておきましょう。
介護保険の保険料はどのくらいかかりますか?
加入年齢や契約内容によって大きく異なります。40代後半なら月額数千円程度から契約できる場合もありますが、60代以降では月1万円以上になることもあります。
掛け捨て型か積立型かでも負担は異なりますが、一般的には「若いほど保険料は安い」ため、早めの検討が経済的に有利です。
介護保険でお悩みの際は「ハレノヒハレ」にご相談ください
介護保険は、将来誰にでも起こり得るリスクに備えるための重要な選択肢です。ただし、その必要性は一律ではなく、貯蓄の状況や家族構成、ライフプランによって大きく変わります。
公的介護保険があるとはいえ、実際には数百万円単位の自己負担が発生することもあり、民間介護保険を検討する意味は十分にあります。一方で、資産や他の保障が整っている人には不要な場合もあるため、「自分に本当に必要かどうか」を冷静に判断することが欠かせません。
たとえば、一人暮らしで子どもに負担をかけたくない方や、老後資金に不安を抱えている方にとって介護保険は大きな安心となります。逆に、十分な資産や既存の保障がある方には優先度が低い場合もあり、だからこそ中立的な立場で一緒に考えてくれる存在が必要です。自分だけで介護保険の必要性がわからない場合は、一人で悩まずにプロに相談しましょう。
ハレノヒハレは「未来すべて、ハレになれ。」をコンセプトとして、お客様一人ひとりの状況やご希望、ライフスタイルなどに合わせた最適な保険商品についてアドバイスを行っています。介護保険の加入についてお悩みの際は、ハレノヒハレまでお気軽にご相談ください(ご相談したいことがございましたら「お問い合わせ」フォームからご入力をお願いいたします)。